天使と悪魔 ダン・ブラウン
 ダ・ヴィンチ・コードを読み終わってすぐに読み出しました。
ダ・ヴィンチ・コードを読み終わってすぐに読み出しました。友人から借りたDVCが、余りに面白かったのでたまらずAmazonでDVCと一緒に購入した物です。 これが面白い! DVCよりも面白いといってもいいほどです。
ストーリーは、相変わらずまずどことも知れぬところで理由も知れぬ殺人が起きて、ラングドンが電話でたたき起こされます。VCDと同じ展開なのですが、考えてみればこちらが先行作品です。
さて、その後はあれよあれよと舞台は一気にヨーロッパへ。突如として語られる(SF畑の人には堪えられない)反物質の恐怖!象徴学の権威ラングドンと反物質がどう咬み合うのか? それは読んでのお楽しみです。
スタトレファンには思わず顔のほころぶ一節もあり。あちこちに見られるラングドンのぼやきのおもしろさも楽しい物です。
われわれにも記憶に新しいコンクラーベが開かれる(つまり法王が亡くなったという設定)、その当日に反物質を使った大規模テロの予告が飛び込むわけです。首謀者はイスラム原理主義者? それともIRA過激派? いいえ、何世紀も前に途絶えたと信じられていたイルミナティという啓蒙主義を掲げる反キリスト教的科学者の秘密結社。その紛うかたなき証拠は最初に殺された物理学者の胸に押された焼き印!
ローマ消滅のテロ予告、行方不明になった4人の枢機卿の殺害予告、と矢継ぎ早に押し寄せる危機の動的な興奮と、ラングドンが持てる知識と推理の機微を働かせて謎を解き明かしていく静的な沈思黙考の対比が話の展開にメリハリを付けています。 行動的な若い女性科学者ビットリアとの(ちょっとべたな)掛け合いも(パターンだけれど)楽しめます。
反物質を封じてある容器が24時間しか保たないという、まるでFOXTVの"24"を見るような焦燥とめまぐるしい展開に読者は奔流に流されるように最後のページまで目を離せません。
以下、読み進める時系列で書いた日記をそのまま上げてみます。英語版を読んだお陰で早く展開が知りたいのにゆっくり読まねばならない、そのじれったさや、反対にゆっくりと展開を楽しんでいる様子が伝わりますでしょうか?
書店へ行けば日本語版が平積みしてあるのですが、こちらを読み終わるまで見るものかと横目で見て帰ってきました。
さて、後半はどうなるのでしょうか。まだまだお楽しみは続きます。
ただいま89章です。
ますます混迷の度が深まって、今一歩のところで時間切れで続く殺人を阻止できず、挙げ句の果てにマスコミにリークするわ、前法王の謀殺説は出るわ、ラングドンは書庫に閉じこめられるわ、進むに連れて首謀者の謎は深まるばかり。
反物質の存在を知り、研究室への入り方を知っている、しかもバチカンの奥に入り込める資格を持った"イルミナティ"の信望者。。。この条件に合う人って、あの人だけじゃん?
早く最後まで読まないと落ち着いて寝られない。
107章まで進みましたがあと30章で終わり。
終わりが見えてくると途端に勿体なくなって読む速度が落ちます。このまま永遠に続いて終わって欲しくないような気分です。しかしまだ見えてきません。真の黒幕は・・・・・・?
時あたかもSWEp.3の試写会を東京・大阪などでやっていますが、こちらでは世の中から取り残された気分で、開き直ってこの本に没頭しています。
DVCに比べてもひけをとらず面白いと思います。ラングドンだって本作の方が遙かに行動派です。殺し屋と水中格闘もすれば空中アクロバットまがいのことまでやってます。かなりの騎士道精神の持ち主で、DVCの学問一筋、学究派から少しイメージチェンしています。
129章・・・・・・もしかして、もしかして、というより あ た っ ち ゃ っ た !! まさかと思いながらもこいつしかいない、読み進むに連れて確信になりました。 でも、でもです。これもしも日本語で読んでいたら早くストーリーの展開が知りたい一心で飛ぶように読んで結局細かい伏線というか、作者がそこかしこにちりばめてあったさりげないヒントに気が付かないでしまったかも知れません。 英文でゆっくり焦る心を制しながら読んだせいか(そうしないと見失ってしまうからw)最大のボスキャラの正体を見破ることができました。いや、めでたい〜☆
この小説、設定に相当無理があると評論にありましたが、いまそれがよっくわかりました。それを割り引いても面白いことには変わりありませんけれどね。
浮かれ過ぎたので少し内容に戻りましょう。息もつかせぬストーリーの展開の妙以外に留意しておきたいのは登場人物の口を借りて述べられる、科学と宗教の今日的意義についての明確な意見です。
下巻中程にある聖職者が、確かに今日の科学はわれわれの宗教に勝利した、しかし科学が解き明かした自然の仕組みが人類に何をもたらしたか?科学が自然への畏敬の念を持ち得るのか?科学の発達がわれわれの精神をどの高みに押し上げたのだろうか? と真摯に問いかける長い演説は、平易なことばと比喩を混ぜた表現で書かれながら、その部分だけ取り出しても読むに耐える名文でした。相容れないと思われる科学と宗教が手を相携えて進んでいく道があるのではないのかという説得力ある訴えがひしひしと 伝わってくる内容でした。
ダ・ヴィンチ・コード ダン・ブラウン

 そろそろ世の中のブームが盛りを過ぎようとするころですが、遅まきながら「ダ・ヴィンチ・コード」です。
そろそろ世の中のブームが盛りを過ぎようとするころですが、遅まきながら「ダ・ヴィンチ・コード」です。「ベストセラーは買わない」「ハードカバーは極力買わない」
この2原則を守って横目で見ていたダ・ヴィンチ・コード(略してDVC)、近隣の図書館に予約を入れたらなんとウェイティング19人目!ということで、 これはもう今年中には読むのは無理か、などと諦めかけていたのですが。内容のおもしろさからか、後続の待ち人への遠慮か、思わず早くも読むことができました。
で、 面白かった!!──ただし借りられたのは上巻のみ。下巻はまたまた予約待ちとなりました。
これはつらい、水から飛び出して地面でぱくぱくやっている魚の状態といいましょうか、腹ぺこの部活帰りに鼻先に出された肉まん状態といいましょうか、 もう一刻も早く続きが読みたくて仕方がありません。そして、「天はわれを見放」しはしませんでした。
毎週通っている趣味の会で(ちなみにこの会では私は品行方正、エンタメ本など読まないような顔をしているのですが)友達の一人が言いました。 「DVCペーパーバックだけど、面白かったよ。辞書片手に読み終えたけど、誰か読まない?」
もちろん、「わんわん、ご主人様。私に一つ下さいな〜」
というわけで、ペーパーバックで後半56章から読み始めました。如何せん、邦訳で読んだ上巻はそれこそあっという間に読み終わったものの、 こちらは日本語で読むほど早くは読めませんが、思ったよりも文章が平易で時折出る宗教絡みの単語チェックをすれば、筋の展開の速さにつられ、つい熱が入って思ったよりも かなり早く読了しました。時間がかかるのはマイナスなのですが、じっくり読むので、訳本で読んでいたら筋を追うのに夢中になって読み飛ばしてしまったかも知れない伏線、微妙な 登場人物たちの振る舞い(それが後で意味を持ってきたりするのですが)をしっかり読み込むことができて、首魁の正体も早めにわかりましたし、何よりも一ページ一ページと繰りながら 展開をはらはらしながら追うことができたのは収穫でした。
深夜ルーブル美術館の展示回廊で起きた奇怪な殺人事件、しかも被害者は館長。ダ・ヴィンチの描いた人体模型を模した死に様の奇怪さと隠されたダイイング・メッセージから 偶然パリを訪れていたハーバード大学象徴学の権威、ロバート・ラングドンがパリ警察から捜査協力を依頼されます。しかしその裏にはラングドン自身が犯人と思われる証拠が上がっていたのです。
身に覚えの無い罪を着せられそうになったラングドンを救ったのが警察暗号解読班の女性捜査官で、しかも殺されたソニエール館長の孫娘のソフィー。彼女の機転でルーブルを逃れたラングドンは ソニエールが、キリスト教会を根幹から揺るがす事実を伝え証拠を保管している宗教秘密結社シオン派修道会の幹部であったこと、千年紀の到来した今、その秘密を公にせんとシオン派修道会を 殲滅せんとする第三の勢力が現れたこと、その謎は自らもシオン派の総長であったレオナルド・ダ・ヴィンチがその絵画の中に隠して描いていたことなどを解き明かし、ソニエールの残したメモの なぞめいた詩文を解読しながら、ダ・ヴィンチの設計による暗号の隠されたクリプテックスを探し当て、友人の英国人で聖杯研究者のティービング卿の助けを借りて英国へ脱出。
フランスの警察の追求をかわし、狂信的なキリスト教の一派オプス・ディの暗殺者から逃れ、もう一人のシオン派総長であったアイザック・ニュートンの墓に隠された暗号を読み解く。 最後の謎を解き明かさんとするまさにそのとき姿を現す真の首謀者の正体! そして隠されたキリスト教の成立にまつわる秘密とは? その在処は?
とまあ、ネタバレを極力避けながらざっとを辿ってもこれは一筋縄ではいかない話だということがわかるでしょう。ダ・ヴィンチ・コードといいますが、本当のところは"ソニエール・コード"なのですね。 さて、これを読んだときに、何の平仄か、先般見た映画「キングダム・オブ・ヘブン」にも描かれたテンプル騎士団、聖杯伝説、 それどころかこの世の楽園 Kingdom of Heaven そのものの考察もキャラクターの口を通じて説明されて、この映画と小説が、 まったく異なるジャンルの異なる文化メディアにも関わらず、一つの大きなキリスト教を核とした文化大系を、期せずして異なった角度から切り込んで 見せてくれていることに気がつきました。
歴史・宗教・絵画、そういった重厚で非現世的なものに端を発する現世的な殺人事件、現象の下に隠された謎を解き明かす知的好奇心を 揺さぶられるようなストーリーテリングは秀逸です。
全米でベストセラーになったのもうなずけますが、日本でも売れに売れたというのが少し不思議でもあります。
単にベストセラーという名前がさらに読者を増やした自己増殖ブームだったのか、それとも「キリスト教を根幹から揺るがすような秘められた真実」 を野次馬根性でのぞき見したかったのか。それともキリスト教云々は抜きにしても謎解きのおもしろさが秀逸だったせいか。
ともあれ、フィクションとはいえ宗教上大きな仮説を(いかにも真実らしく)述べることが容認され、 それを知的遊戯として多くの人が受け入れるだけのゆとりができた、言い換えれば精神的成熟が高まったことは大いにうれしいことですね。
光の帝国 ── 常野物語 恩田 陸
 初見の作者の本を読んで、しまった・・・と思うことが多々ある。
初見の作者の本を読んで、しまった・・・と思うことが多々ある。今まで自分がその作者を知らなかったことを悔やむ気持ちである。
なぜもっと早く手に取らなかったのか、と忸怩たる思いである。
恩田陸、彼女もその一人だった。
「夜のピクニック」が2005年度第2回本屋大賞をとったとどこかで目にした。それが心の隅に引っかかっていたのか、それまで、 「そういう作家がいるな」くらいにしか意識していなかった作家を、ふと読む気になって手に取ったのが新刊の文庫「劫尽童女」だった。
正直なところ、この作品にはそれほど惹かれなかった。読みやすく、するする馴染んで入ってくるプロット、しかし先が読めてしまう展開、 宮部みゆきを最初に読んだときと同じ読後感をもった──確かによく書けているけれど、物足らない。同人っぽい若い人の文章だと思った。
しかし、新しい作家の本は最低3冊は読まなければ、本当に自分にしっくりくるお馴染みになって今後読み続けるか、それとも、どうも波長が合わないと手出しを控えるか、 その判断は容易にできない。
大阪駅の書店で恩田陸の名を探して3冊文庫を買い込んだ。内容をじっくり吟味している暇はなかったが、それが却って功を奏した。
手に取ったのがこの「光の帝国」──何とも大げさなタイトルではあるが、その意味がわかったのは読了後、 じわじわと感慨がわいてきて、後から後から涙がわいてきた後だった。
こころがあたたかくなる話である。
実に日本的な話である。
一昔前のSFファンなら聞いたことがあるかも知れない。ゼナ・ヘンダーソンの「ピープル・シリーズ」 (「はるかなる旅路」)、わたしはこの短編集が大好きだった。そして同じ気分を思い出させるクリフォード・D・シマックの中・小編、特に「中継ステーション」の郷愁と甘い感傷。
短い10の短編からなる「光の帝国」、その初めを読んだだけで上記のピープル・シリーズを思い出した。 (作者あとがきに、やはりピープル・シリーズを念頭に置いて書いたとあったので納得である) しかし、もちろんこの作品は単にヘンダーソンの小説の設定の翻案に終わってはいない。
むしろ、常人とは異なる能力に恵まれた一族の人々が、歴史の裏に表に姿を仄見せながら生きていく様を、恩田さんという若い作者が、 日本という風土のもとで詩情豊かに描き出す様は、ヘンダーソンを遙かに越えて私たちの心に響いてくる。
東北のどこかに想定された常野(とこの)に住む人々(これも柳田国男の「遠野物語」を連想させて重層的である)、彼らには常人にない能力がある。
大量の書籍、音楽、果ては個人の生涯すらも「記憶」して、しかも総体的に「再生」できる能力を持った一家、 人の将来を水鑑の中に読める女性、何百年も生きて一族の語り部になっている老人、遠方の物を見聞きできる男、空を飛び、時間すら遡行させられる女性、彼らにしか察知できない見えざる敵── その昔は常野に暮らしていた一族が、現代全国に散らばってひっそり暮らしている。
彼らは、世を忍ぶ仮の姿に苦しむスーパーマンでもないし、おのれの超常能力を呪いだと重荷に思うスパイダーマンとも違う。 彼らは自然体で世に溶け込んでおのれのあるがままの姿を保ちながら生きている。何かのために自分たちはいるのだという漠然とした使命感を持ちながら。
10の掌編はそれぞれ別の話を物語りながらも、俯瞰してみると、ピースが独りでに寄り集まって一つの大きな絵を描き出すように巧妙に配置されている。 一つの話が後になってもう一つの話と関連を持ち、さらに大きな物語になっていく予感を残しながら終わるともなく終わっていく。
表題作「光の帝国」は中央に配置された物語で、戦争が敗色が濃くなりつつあった時代に常野に戻ってきた人々を利用しようと軍部の手が伸びてくる暗い物語。
一族の語り部たる長命のツル先生と子供たちの哀しくも心あたたまる物語。ツル先生の足跡は他の物語にも見え隠れしてエピソード間の縦糸を繋いでいる。 飄々とした風貌と達観したような生き様の中に、はっとするような若々しさをもつ魅力ある人物。
実は「光の帝国」以外にもう一編涙を禁じられない物語がある。「光・・・」の2話後の「黒い塔」がそれである。面白いことに惹かれる箇所は物語そのものよりも、 サブストーリーとして描かれる主人公の女性を死んだ友人に代わって我が子として育てた父母、特に父親の姿であった。
これはまったく個人的好みの問題なのだが、どうも私は親モノに弱い。親が子を思うのはあったり前といえばそれまでなのだが、特に言葉、映像になった親が 子を思うくだりになると涙が出て止まらなくなる。
「黒い塔」で主人公は父親の死期が近づいているというのに、こだわりを捨てられず、心を開くことが出来なくて苦しんでいる。 しかし人の一生を記憶に「しまって」おける女性から、昔の父の姿を、声を目の当たりに見せられて一気に心が解けるくだりは涙なしには読めないところだった。
作者が惜しげなくもてるアイデアをちりばめたと語っているように「光の帝国」はさらに大河物語になる予感を漂わせて終わっている。 登場した人々のその後の姿を見てみたいと切望しているのは私だけではなかろう。是非とも続編が期待される所以である。
ホミニッド ロバート・J・ソウヤー
 学生時代の人についたあだ名っていうのは、なかなか言い得て妙というものが多い。
学生時代の人についたあだ名っていうのは、なかなか言い得て妙というものが多い。特に高校、大学時代のあだ名はペダンティックさからいっても、時には残酷なくらい「当たってる」ものが多くて、今思い出しても思わず笑いがこみ上げてくる。
たいていどこの高校にも「ガンジー」みたいなやつがいただろう?
さて、私の大学時代にクラブに、「ねあんちゃん」なるあだ名をちょうだいした人がいた。
「ほら、あのネアンだよ」といわれて、なるほど彼の風体は天然の縮れ毛にやや幅広い鼻梁、広いひたいにがっしりした口。
いや、申し訳ないことだが、思わず、うふふと笑ってしまった。しかも彼は理学部で原子理論をやってたんじゃなかったっけ。
その外観と頭の中身のギャップがさらにまたおかしさに拍車をかけた。
(今にしてみれば、本当に申し訳ない、でも彼もまた大勢の人に的確なあだ名を進呈していたのだからおあいこかも)
さて、枕が長くなりすぎたけれど、ロバート・J・ソウヤーの最新作 「ホミニッド──原人」を読んだとき、まさに上記の友人を思いだしてしまった。
3部作、ネアンデルタール・パララックスの第1作目、続刊は今年中に発刊予定で、今から心待ちにしている。
私たちのこの宇宙では、ネアンでルタール人は絶滅してクロマニヨンの子孫たるホモ・サピエンスが支配的な立場にいるが、 無限にある並行宇宙の一つではネアンデルタール人が進化を遂げて地球のドミナントになっている。
ネアンデルタール人、ポンターは量子物理学者、大型量子コンピューターの実験中に処理能力を超えた過剰な演算にコンピューターが並行宇宙の量子にまで接続してしまい、 結果的にこちらの宇宙と一時的に門(ポータル)が開いてしまった。ポンターはこちらの宇宙のまさに同じ場所、同じ時間にニュートリノ観測所の重水の満たされてたタンクの中に出現する。
こんな風に始まった話は、突如として現れた男がネアンデルタールであることを確認する遺伝学の専門家の女性の目を通して描かれる。
大騒ぎがおこり、群がるマスコミをかわし、意思の疎通が始まり、感染症の危機を乗り越え、双方向カルチャーショックを体験し、何とか帰る方法がないか模索する、まさに山あり谷ありの奮闘。 あちらの世界では優秀な科学者で父親で壮年の男が、こちらへ来た途端に絶滅種の「原始人」と確認され、インプラントされた携帯コンピューターの助けを借りて驚異的な速さで言葉を学習して こちらの協力者たちと意思を通じさせ始めるのだが、まったく異なる社会通念、生活習慣などで、孤立感はぬぐえない。
ところがこの話のすごいところは、ポンターが消えたあちらのネアンデルタールの宇宙の時間進行も同時に描いているところ。
しかもあちらの時間単位から、社会構造、まったく異なる家族構成、生殖のシステム、果ては裁判制度まで一部の隙もなく構築してあるソウヤーの手並みこそ見事である。
ポンターの失踪で「殺人罪」で告発された研究と生活上のパートナーの苦境、父親を殺されたと信じる娘の葛藤、 ところが量子コンピューターの暴走でポンターが「転送」されたのではないかという結論に達して、なんとか再度接続を試みる「被告」。法廷物サスペンスまで読ませてくれるのだ。
圧巻は、現在すこしずつ明らかになりつつあるネアンデルタール人の行動や社会(?)の諸説を取り入れながら、ソウヤーが空想を縦横に駆使して構成した彼らの社会。
クロマニヨン系の人類より遙かに隆々たる体躯をもつ彼らは、一旦激情に飲まれて殴りかかれば相手を殺しかねない。
ゆえに徹底した感情統制を行って、厳罰を科することによって犯罪を未然に防いでいることとか、経済基盤が農耕社会でないだけに、これも徹底した産児制限をおこなって人口の爆発を防いでいる、その結果、少数の人口、豊かなゆとりのある社会が実現している。
しかし「すばらしい新世界」のような強権的な管理社会ではないところが、とても好感が持てる、あくまで理性的でゆとりのある、こちらから見ればいわば理想的な安全な社会なのだ。
ポンターの視点から、こちらの社会を見ると矛盾だらけで、「飢餓」に何億もの人が苦しんでいる状況が理解できないでいる。
しかし両者の社会構造の違いが、実はネアンデルタールとクロマニヨンという生物学上の相違に端を発するものだという視点は新鮮であり、とてもおもしろい。
話の展開で、いくつも、「ああ、ご都合主義だ」と思えるところはあるのだけれど、それで決して話がつまらなくなるわけではない。
元々ここまで突飛な構想であると、ご都合主義をもちださなければ話がまとまらない。むしろ、ソウヤーの手並みがいいのでご都合主義が快感ですらある。
へえ、そうきましたか、ふーん、なるほど! ってわけ。
ポンターと遺伝学者のメアリーとの心のふれあいもみずみずしいし、分かれてからの二人の前向きな生き方もとても共感できて、好感がもてる。
というわけで、久々に一気読みしたソウヤーの新作だった。
続刊の刊行を首を長くして待たないといけないな。
ダーリンの頭ン中 小栗左多里 & トニー・ラズロ
 本書の前作にあたる「ダーリンは外国人1・2」は、外国人の夫と日本人の妻の共同生活での感覚のずれや思いもかけない珍事態について軽妙洒脱な漫画で描いて、ベストセラーになりました。
本書の前作にあたる「ダーリンは外国人1・2」は、外国人の夫と日本人の妻の共同生活での感覚のずれや思いもかけない珍事態について軽妙洒脱な漫画で描いて、ベストセラーになりました。本作はその後、雑誌「ダ・ヴィンチ」に連載した後続を単行本化したものです。
連載中から何度か目にしていて、今回の内容はややペダンティック、 言語フェチには楽しいけれど一般受けするかな?と老婆心ながら多少の危惧も。
日本語以外の言語に少し足を突っ込んでいるので、わたしにはとても面白く、今まで特に確固とした根拠なしにそうだと思いこんできたことが、 ちゃんと説明されていたりして、頷くところ、ぽんと膝を打つところ、へーっと感心するところ、多々ありました。
言語好きには頷ける共通の興味の持ちよう、言葉についての「こだわり」がわかるのよね!
語源の拡がりなど、今までそれに関した本や新書などいくつか読みましたが一番面白く紹介してあり、しち難しい歴史的検証を述べる語源論の本よりずっと取っつきやすいものでした。
語源辞典もこのノリで全部小栗+ラズロのコンビが書いてくれれば、画期的な辞典ができるのに、惜しい!
一般受けは難しいかも、といいましたが、内容の面倒くささを補って余るのが小栗左多里のあそびのある絵と独特のつっこみ。 彼女の話題の料理の仕方が絶妙なので、今まで言語としての英語に興味を持っていなかった層の掘り起こしが期待されますね。 私としてはさらにこの手の続編を期待しています。
世の判定は如何に?
西の善き魔女 荻原規子

 長らく気になっていた作品を読みました。
あちこちのファンタジー系サイトを覗くと必ずお目にかかるタイトルだったからです。
長らく気になっていた作品を読みました。
あちこちのファンタジー系サイトを覗くと必ずお目にかかるタイトルだったからです。文庫化でやっと手にとって、これも教養のうち、参考程度に読んでおこうかなという不純な動機ではありました。
結論からいうとかなりはまってしまいました。少女漫画(それも少しレトロな)のノリ。
第1巻から、ばりばりスタンダードの筋立てです。
出奔して身分を隠した王女と学者の父の間に生まれて、出生の秘密を知らずに育った少女が偶然の重なりで出自を知り、 しかも危険が迫って父とは生き別れ、慣れ親しんだ家から逃げ出して、幼なじみのエキセントリックな少年と、 ひょんなことから庇護してくれることになった有力者侯爵家の掛人となり・・・貴公子は出てくるわ、従妹の女王候補の可憐さと精神の強靱さを備えた少女と意気投合するわ、 暗殺者も出るわ、何でも出るわ、で盛りだくさん。
ルーカスの神話ではありませんが、秘められた出自、苦難の旅、アイデンティティーの発見と定石通りに筋が進む様は小気味よいくらいです。
第2巻で、舞台は外界に閉じられた修道院付属の女学院。良家の子女が集まり一般知識・礼儀作法はもちろん、陰謀術作の渦巻く宮廷での身の処し方、 果ては女性という武器を用いての対外政策(いかに外国の要職にある男性を籠絡するか)まで、教えてくれる、おとろしいところ。
生徒内部にも後ろ盾となる出身家別に陰湿な派閥ができて、新入生を恐ろしい洗礼が見舞う・・・・・・
これ、まさに少女まんが、さらに学園祭の舞台は宝塚。
ここまでくると、本当におもしろい! 作者も確信犯的に書いているものだから、面白いように予測通りの展開や典型的な人物が出てきたり、とにかく楽しめました。
文庫版で出ているのはまだ1・2巻のみ。 さっそく続きを読むために図書館へGO! 3〜5巻まとめて借りてチェーン・リーディングで読み切りました。
王国の南には龍が出没、許嫁の侯爵家の息子は龍退治の騎士になって遠征。少女は身を少年に窶して後を追います。 一角獣に乗って龍と戦う騎士はさながらセント・ジョージです。龍と出会い、世界の果てを見て、次期女王選定の渦に巻き込まれて王国に帰る少女たち。
待ちかまえていたのは不思議な道化師と賢者、そして伝説的な現女王のお出まし・・・・・・かいつまんでイベントを上げただけでも、そのめまぐるしさ、多彩さにためいきが出てきます。
最後のSF落ちは、ま、仕方がないでしょう。結局ファンタジー世界を構築すると合理的に説明するとSF落ちになってしまうんですね。
旧新書版は挿絵がまた、少女まんがそのもので、ちょっと外で読むのは気が引けましたw
舞台となったファンタジー世界に複数存在する国家間の複雑な国際的または経済的な力関係とか、王国内の後継者選びにまつわる権力争いなど、 表面的でもっと掘り下げればずっと複雑な様相を呈したかもしれないお話ですが、そのへんはさらりと軽く流していくあたりは物足りなさを感じますが。
最初から主人公のフィリエル、誰かに似ている、話し方、考え方・・・・・・う〜〜ん。
そのうちはっと思い当たりました。「ガラスの仮面」の北島マヤちゃんのイメージでした!
このレビューは決して「西の善き魔女」をけなしているのではありません。念のため。
それどころか一気読みさせられるほど面白かったのです。西洋風ファンタジーの衣を纏っていますが、これは純正日本製のファンタジー、 その上は「リボンの騎士」にまでルーツをたどれるような気がします。
魔術師・イリュージョニスト ジェフリー・ディーヴァー
 もしも、ほとんどどんな人間にでも一瞬で変身できるような魔術師が連続殺人の犯人だったら。
もしも、ほとんどどんな人間にでも一瞬で変身できるような魔術師が連続殺人の犯人だったら。もしも、現場に残される微細な慰留物まで、捜査を誤った方向へ導く(誤導)ために仕組まれた物だったら。
さまタマさんもお気に入りになったジェフリー・ディーヴァーのリンカーン・ライム=シリーズ第5作目にして最新刊、「魔術師(イリュージョニスト)」 でライムとサックスたちが相手にするのはこういう犯人です。
魔術師はコインを消す、帽子から鳩を出す、カードのトリックを見せる・・・・・・こういう普通の小手先を使って人の目を欺くだけでなく、人の心理をも操ります。 見せたくない物から注意を逸らすテクニック、思いこみを誘発して目撃者の目を欺く・・・・・・
ディーヴァーの小説の一つのスタイルでもありますが、冒頭から犯人のイリュージョニスト=マレリックと名のる男の読者への挑戦状とも受け取れるような「口上」が述べられます。
これはマレリックが社会に突きつけた大胆不敵なマジックの口上であると同時にディーヴァーが読者に掲げた挑戦状でもあるのです。
さまざまなマジックの大出し物を「見立て」にした残虐な殺人事件、警官の目の前で閃光と共に消え失せた容疑者、ほんの数瞬でまんまと別人になりすまして悠々と人前を歩いて行った 容疑者。被害者たちからはなんの関連も見いだせないままに、次の殺人が予想される刻限が近づく・・・・・・
「エンプティー・チェア」「石の猿」と先行2作がわりに小振りだったので、一時はライムシリーズもマンネリか、それともこれで終わるのかと気を揉まされましたが、 ディーヴァーの言葉を借りれば、「石の猿」執筆中にどうしてもライムの物語で書きたい物ができた、というのが、この魔術師の物語だったのです。
まさに同時代の小説、9・11のテロ事件にも言及があり、そちらの社会性を持つ方向に進むのか、と思いきや、一転して華麗なサーカスを彩る魔術師の大イリュージョンをステージで完結させないで恐ろしくも現実世界に広げてきました。
なにせ、彼はイリュージョン、早変わり変身、腹話術、ピッキングと人目を欺くエキスパート中のエキスパート。本来なら個人の特定が容易になる明らかにわかる手の傷跡まで捜査の攪乱に使われてしまいます。
さしものライムも、現場検証から得られる証拠が信用できないかもしれない、という手詰まりを感じて今回は新しいキャラ、カーラが登場します。
カーラはちょうどサックスの小型版といったかんじ。一つこと(マジック)にとことん入れ込んで厳格な師のもとで修行している、その努力のやり方がアメリアっぽいのです。
師匠に内緒でマジックの手法、道具、そして心理操作=誤導についてライムたちに的確な情報を与えてくれます。
サブストーリーに、巡査部長への昇進テストを受けるアメリア(このシークエンスは緊迫感があってとてもすてき)、老人介護施設にいる痴呆症の母を足繁く通うカーラの心情などが絡み、さらに介護士のトム、 刑事のセリットーやベルなどいつもの面々がおなじみのキャラクターで登場します。彼らの書き込みもまたディーヴァーの小説を楽しむ上で欠かせない遊びになっています。
一度は誤導をかわして、証拠による推理から殺人を未遂にくい止めるものの、裏をかかれてライム自身が危機に陥ったりもします。 そして、マレリックの殺人の目的は純然たる遺恨からの憎悪だと思われていたのが、政治的な裏のある殺し屋として動いていたことが発覚・・・・・・しかし、これもまた誤導。
かくしてライムまでか読者も何が真実で何が虚偽か、物語がどのように動くのかまったく余談を許さなくなります。
最後の大出し物「燃える鏡」の被害者は誰か。テロに見せかけたサーカスの観衆の大量殺戮は防げるのか? カーラは、アメリアは、ライムは、間に合うのか?
最後まで息もつかせぬどんでん返し、そして最終の局面に近づいて、初めて読者はこの物語すべてが読者を誤導させるべく作られていたことに気が付くのです。
原題 Vanished Man 消された男、これがつまりイリュージョニストだったのです。犯人だと思われていた男はもう消えていた。代わりにマレリックがその男に成り代わりイリュージョン殺人を犯し最後にその存在を消す、消え失せることになっていたのです。 つまり犯人の正体は最初からこれ以上明確なことはないほどはっきりと目前に提示されていたのです。
他のお楽しみには、昇進試験に横やりを入れる議員と敢然と戦うアメリアや、「悪魔の涙」で友情出演したライムに今度はお返しとばかりに懐かしい声を聞かせてくれるキンケードなど 内輪ネタ的ではありますがにんまり楽しませてもらいました。
最後にやはり一番印象に残るのは、黄色のカマロを時速140kmでぶっ飛ばす颯爽としたアメリアの姿です。今回はカマロ、大破しちゃいますがね。
機長席からアナウンス 内田幹樹
 ぶらりと立ち寄った書店で見つけ、帰宅してから、
実は急ぎの仕事があるので、仕事をそっちのけにして読みふけりました。
ぶらりと立ち寄った書店で見つけ、帰宅してから、
実は急ぎの仕事があるので、仕事をそっちのけにして読みふけりました。助詞の使い方間違っているって? いいえ、仕事があるので(逃避するために)読みふけったんです。
飛行機嫌いが飛行機の本を読む。わ、自虐的行為だ、なんていわないでくださいね。怖いのに人一倍興味は持っているのです。
さて、ジャンボジェットの機長なんて、ちょっとかっこいいじゃない?
古くはキャッチ・ミー・イフ・ユー・キャンの時代から、あの制服にばりっと身を固めた姿はいかにも沈着冷静、有能を絵に描いたよう。
でも、本書を読んで、さもありなん、キャプテンだって人の子だと安堵いたしました。
フライトアテンダントのお姉さんとの(所属の違いからくる)指揮権?を巡る軋轢とか、国際線の機長の方が国内線をたくさん飛んだ人より離着陸が苦手?とか、 本当にUFOらしきものを目撃? でも写真を撮るとたたり!があると撮影を拒んだ副操縦士とか、 海外に飛んでも時差惚けでホテルでぼや〜っとして日を送るとか、ジェットコースターに乗っても、どのあたりで加速したりGがかかるか予想できるのでちっとも怖くないとか。
エンジンが一機故障!でも離陸を緊急中止しても修理する部品が手に入らないから、このまま8時間飛んでイギリスまで行ってしまおう、とえらく気楽なフライトとか、 どこの航空会社の飛行機が離着陸に時間がかかるとか、 気流の悪いところでは乗客の飛行機酔いを防ぐためにわざと少し怖い思いをさせるとか etc.
パイロットとその就業環境について、ややネタバレと著者のアクが色濃く出ているけれど、内幕ものとしてとても楽しく面白く読めました。
さもあなん+へえ、そうなのと、同感と意外性が交互に楽しめる軽い読み物でした。
ほんとのところ、こういうの大好きなんですよ。
クリスマスの思い出 トルーマン・カポーティ

 クリスマス・シーズンになると読み返したくなる本があります。C・ディケンズのクリスマスキャロルはちょいと古くさいし好みではありませんが。お薦めは何といっても、トルーマン・カポーティの「クリスマスの思い出」に尽きます。
クリスマス・シーズンになると読み返したくなる本があります。C・ディケンズのクリスマスキャロルはちょいと古くさいし好みではありませんが。お薦めは何といっても、トルーマン・カポーティの「クリスマスの思い出」に尽きます。60才を越えた老嬢と7才の僕、それに犬の二人と一匹だけのひっそりとしたクリスマス。一年中節約してたくさんのケーキを焼くおばあちゃん、必ず一つを大統領にも贈るナイーブな心の持ち主です。
二人で森へ出かけ樅の木を切り出す、手製の飾り付けをして、本当は何か素敵なものをあげたいと思いながらお互いにプレゼントに手作りの凧を交換することになります。 しかしこの質素でささやかなクリスマスの楽しみも長くは続きません。別れが訪れて二人は二度と会うことはないのです。最後のクリスマスの様子が清冽で端正な文章で綴られていきます。読む者の心まで洗われるようです。
もう一つあげたのが、このカポーティの小説を元に山岸涼子が漫画化した「クリスマス」。ここの画像が「クリスマス」の扉だったのですが、タイトルだけ短編集用に変えられて使われています。
クリスマスの思い出、実は読んだのはこちらが先でした。それまでほとんど少年漫画専門に読んでいて、少女漫画は特定のものしか読んでいませんでしたが、偶然店頭で立ち読みして、引き込まれてしまったのがこの短編。 その場で買いました、もちろん。
なんとしみじみとしたいい物語だろうと思っていましたが最後のコマに"A Christmas Memory Truman Capote"と小さく入っていることで、やっと原作はあの"ティファニーで昼食を"で有名なカポーティだと知りました。
お涼さまの作品も原作に負けず劣らず素晴らしい(ある意味彼女の最高傑作ではないかと思えるほど)心に残る作品です。老嬢、ミス・スックの童女のような無垢さ、人の心の交流、生あるものへの慈しみが余すところなく書かれていて、それだけに最後の澄み切った喪失感は忘れることができません。
わけもなく素直に感動を語れる二つのクリスマス物語です。
アブダラと空飛ぶ絨毯 アイアナ・ウィン・ジョーンズ

 この一文は2002年1月に読書日記に書いたものを転載しました。
この一文は2002年1月に読書日記に書いたものを転載しました。「魔法使いハウルと火の悪魔」(1986)の姉妹編にあたります。
登場人物も舞台も一新されて「ハウル」続編と歌いながら、そのご当人はほとんど出てこない(?)続編です。
「魔法使いハウルと火の悪魔」の舞台設定がかなり取っつきにくい───それだけ独創的だったということですが───ものでしたが、一旦その世界になれて沈潜すると、 奇妙な設定が妙に実在感を持ってくる、その不思議な浮揚感がたまらず、思わず飛んでしまいました。
姉妹編なら、また再びそれに類する楽しさを、いや、それに倍する 新しい展開を与えてくれるのではないか……その期待にこの本は答えてくれるのでしょうか?
最初手に取ったとき、少し首を傾げました。というのも「アブダラと空飛ぶ絨毯」 このタイトルがいかにも手垢の付いた響きがあったからです。
どうもイギリス辺りから見ると中国、日本は余りに遠くて異質すぎて料理しにくい、料理しても出来の悪い マダム・バタフライになってしまって、それこそ長崎で外縁の障子(!)を開けると、そこには天晴れ富士山が見えたり、何とも不可思議な着物とも湯上がりガウンともつかない 薄物をしどけなく(だらしなく)羽織ったゲイシャガールがパラソルをくるくる回したり……それが日本だとしたら、お話がどんな名作でも日本人として夢中にはなれないでしょう。
話題がそれましたが、結局余りに遠い極東はファンタジーといえども地に足の着いた物語の舞台にならない。そこへ行くと中近東は、そのかみ千夜一夜の時代を想定すれば 西洋からはオリエント、極東からはオクチデント、二つの大きな文化圏の間にあって双方からファンタジックな空想の翼が広げられる処。全く未知の世界でもなく、 想像の余地をたくさん余している処。
「アブダラと空飛ぶ絨毯」はまさにそんなアラビア、ペルシャを彷彿とさせる舞台で幕を開けます。
アブダラ(音の表記だとアブドゥーラが近い)は父を亡くしたバザールの絨毯売り、怪しげな男からすり切れた"空飛ぶ絨毯"を買い、眠ったときだけ飛ぶ絨毯に乗って夢うつつのうちに 不思議な庭園を訪れ、美しく賢い「夜咲花」の姫君と巡り逢って、(大抵のお話のように)自分の身分を"王子"と偽ったアブダラは王女と駆け落ちしようと企みます。
ところが後少しというところで突如現れて「夜咲花」を拐かすのが、これまたお馴染みの「魔神(ジン)」。
お定まりはまだまだ続くと思ったのが、徐々に流れが変わってきます。
王女誘拐の罪で投獄されたアブダラを救助に現れたのがなんと、バザールのお隣さんの飼っている犬、それも揚げたイカが大好きという……
てんやわんやで重力も物質の質量保存の法則も無視して難を逃れたアブダラが砂漠で出会ったのが、悪辣な盗賊。
絨毯を奪われる代わりに魔法の瓶を手に入れて…そう、今度は瓶の中の「精霊(ジニー)」の登場。
ジョーンズともあろうイマジネーションの才人がどうしてここまで 陳腐な道具立てを考えたのだろう、これが上に書いた「西洋人」の限界だろうかと真剣に考えてしまいました。
しかし妙に現実主義的なアブダラや女性解放論者のような「夜咲花」の姫君の口から出るのは、昔臭い筋立てのキャラクターの台詞とも思えず、 ともかく先へ。
人が良さそうなくせに、妙にすねている瓶のジニーに連れて行かれたのが、いよいよハウルの本拠地、"ヨーロッパ風の"インガリー国(もろにイングランド)
しかしハウルは失踪して行方不明、偶然知り合ったのは傭兵あがりの冴えない男。野宿をすれば黒猫の親子に見初められるし、ジニーとの約束の「毎日かなう一つの願い」は周囲の人間に無駄遣いされるし……
八方ふさがりのアブダラが智恵を絞って考えたのが、利己的な願いを一切止めて、利他的な願いだけをすること。そこに至るアブダラの論理はなかなか見物です。
こうやって登場人物がどんどん増えるのに一向に物語の後ろにある糸が見えてこない、ちょっとジレンマですね。
それが最後の4分の1くらいであれよあれよという間に皆がこぞって「空中の城」へとたどり着き(この旅の描写はきれいです、ロケットに乗って衛星の周回軌道まで上がると このような景色が見えるかも)、「夜咲花」たちの知性と自助努力でジンの呪いを解き、やっとハウルの登場となります。
しかしお話しは見たとおりではないということを知らしめたのもこの辺り、如何に多くの、さりげなく置かれた手ががりを見落としてきたか、もっと早く気がついてしかるべきだったと 臍を噛むのもこの辺り。
読み終わって、すぐにまた最初から目を通し直し始める、ジョーンズの作品に共通するのはこの読者を一杯食わせる巧みさ、構成のすばらしさです。
一見垢の付いたような題材で始めて、読者を油断させておいて、一気に頭をかき回してくれるようなすごさが、またたまらない魅力になっているのです。
魔法使いハウルと火の悪魔 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

 宮崎駿監督がアニメ映画化したために急激に注目を集めた原作です。ただアニメ化決定以前からのジョーンズ・ファンの一人としてアニメ化に危惧を抱いた一人でした。
宮崎駿監督がアニメ映画化したために急激に注目を集めた原作です。ただアニメ化決定以前からのジョーンズ・ファンの一人としてアニメ化に危惧を抱いた一人でした。公開された映画を見て、やはり原作の持つ独特の辛口、ドライでユーモアたっぷりの独自の雰囲気はありませんでした。残念。
Howl's Moving Castle は決して某人気俳優とベテラン女優が甘い声を出す純愛ロマンス路線のお話じゃないのです。ストーリーは複雑に入り組んで読者を惑わします。
映画では端折られたり変更されて部分を少し取り上げてみましょう。
ソフィーにはレティーとマーサの二人の妹がいます。マイケルも子供じゃなくて、気が良くて頼りない見習いの若い衆です。(しかも、話が進むと妹レティ(実はマーサ)の恋人だったことがわかるし) かかしの頭の蕪は腐って臭いし、執拗にソフィーをつけ回すこと不気味です。
後にかかしはインガリー王の弟、プリンス・ジャスティンで、犬はパージファルという立派な名前を持ち、かかしと犬は荒れ地の魔女に破れたハウルの前任者サリマンとジャスティンの身体の寄せ集めの産物だったことがわかります。
サリマンといえばそもそも男で、もう長らく行方不明。荒れ地の魔女征伐を命じられて返り討ちにあったとか。(サリマンも本名サリヴァンというイギリス人だったことも明らかになります)
ばあちゃんになったソフィーはMrs.Noseといわれるくらいお節介焼きの詮索好き。若かったら絶対こんなこと言ったりしたりしないわ、などと思いながらあっと驚く大胆なことをします。
ハウルとソフィー、カルシファーを巻き込んでの皮肉当てこすり合戦は読んでいて小気味いいほど。
荒野の魔女は腰砕けになって「要介護おばあちゃん」になんかならない、最後のハウルとの壮絶な闘いでひとかたまりの骨になってしまいます。
ソフィーが呪いをかけられたのは要するに嫉妬した荒れ地の魔女の相手取り違い。
ソフィーがハウルの所にしつこく居着いたのは、まずはカルシファーと契約して呪いを解いてもらうため。 次に女たらしのハウルが妹レティをその「毒牙」にかけようとしていたから、なんとか防ごうとして。
ハウル/ハウエル・ジェンキンスは黒の取っ手のドアからふるさとの現代イギリスのウェールズへも出入りしていて、そこでの甥の宿題の詩がかれの命運を左右する呪いになっていたこと。甥の学校の先生が(これもハウルがひっかかる美人だけど)実は荒地の魔女の契約している悪魔だったこと、などなど上げればきりがないほど、複雑で人間関係が入り乱れるもっと大人のお話。
この複雑で立体的な構造を持った珠玉のファンタジーを、映画では悪魔と契約を結んだハウルが力を行使するたびに徐々に人間らしさを失っていき、それをソフィーの愛が阻止するという単純化したおはなしに還元してしまったのは残念の極み。 緻密な構成を持った原作を大幅に簡略化してしまったのに登場人物を原作のまま踏襲したので絡みの説明がつかなくなったり無理に違う役割を与えたりしたので、キャラクター設定に違和感が出てしまいました。折れ谷の妹=マーサのことも一言で片づけられてその後始末はなされていません。
大事なソフィーの持つ魔力──話しかける物に命を与える力──それが帽子に魔法をかけ、杖に魔法をかけ、つくろったハウルの服に魔法をかけ(こともあろうに「女の子を夢中にさせる服ね」といったから自分もその魔法にかかってしまうというオチつきなんですよ)その力について言及がないでしょう?
行方不明のサリマンの捜索にでたプリンス・ジャスティンも、結局魔女に捕らわれて二人がバラバラにされてかかしと犬にされていた、サリマンの頭は頭蓋骨になってハウルの城の仕事台の上に乗っていたという、ちょっとグロい設定もぱあになりました。 荒地の魔女とハウルとの魔法合戦ではお互い変身ごっこをして大立ち回りをしますが、周囲の人は最初こそおもしろがって見ているものの、長引くにつれて退屈して家に帰り始めるところなど、うーんドライだと感心。
荒地の魔女がハウルに執心だったのも元はハウルがちょっかいかけたから(いわば変形色恋沙汰だったわけ)。
魔女の呪いが、形而上学的な詩の一節一節が実現して行くにつれて効果を発し始めて、ハウルやソフィーが回避しようとすればするほど逆に実現していく過程は「恐ろしさ」を感じます。 ドライさと恐ろしさがこのお話の裏に控えていることに気づいた人がどれくらいいるでしょうか?
ソフィーが年寄りになってから厚顔無恥で押しの強いキャラになってしまったと不満げに書いていらっしゃる方がいましたが、私が思うにこれはソフィーが避けて通れなかった自己実現だったと思います。
「三人姉妹の長女は何をしても失敗する、長女だから幸運には恵まれない」そう思いこむことでソフィーは自縄自縛になっています。しかも自分の強力な魔法の力が働いていますしね。
この殻を破ったのが肉体の変化とそれに伴う「失うもの無しの強さ」をバックにした精神の変化。引っ込み思案で寛容だった自分から、好奇心旺盛で計画性には欠けるものの何でも徹底的にやらないと気が済まない 頑固な性格の強い意志をもった女性への変容と自覚。結局ソフィーの「運試しの旅」はめでたしめでたしになるのです。
ハウルがどうしてウェールズから魔法の世界の方へ来たのかその説明はなされていませんが、所々でハウルが漏らす言葉──自分はウェールズが好きなのにあちらはぼくを好きじゃない、姉はぼくが妬ましい。 なぜって、自分は人からまともに見られるのにぼくはそうじゃないから───などからわかるように、ハウルも故郷では容れられず大きな疎外感をもってこちらの世界に移ってきたことが想像されるのです。
流れ星と契約して自分の心臓を与える代わりに想像を絶する力を得る、でもそれは破滅へ繋がる道。ハウルはそれと知りながら、完全では無いにしても心の空虚さをいくらか埋めてくれるカルシファーとの 関係を断てないでいます。本質的に人との繋がりを大切にする寂しがりやなのです。
終盤に進むに従ってソフィーはますます意固地に我を押し通すようになりますが、これは最後に強い意志をもって魔女の所に乗り込むための布石であり、さらに荒地の魔女の悪魔からカルシファーを取り戻し、ハウルの心臓を元に 戻すだけの決断力と行動力を蓄積するために辿らなければならない自己改革だったのです。
ハウルの心臓が無くてもカルシファーを生き延びさせるためにソフィーの「ものに命を吹き込む魔力」が必要だったのも作者の最初からの計算だったようです。
読み直すたびに新たに作者がこっそり仕組んだちょっとした罠に気がついて、そのたびに新たな楽しみが増していく、そんな本と出会えてよかった。
エンプティー・チェア ジェフリー・ディーヴァー
 ジェフリー・ディーヴァーのリンカーン・ライム・シリーズ第3作です。まだハードカバーでしか出版されていないので図書館を利用。
次作、次々作の「石の猿」「魔術師(イリュージョニスト)」同様、ウェイティングした後、やっと借りられました。
ジェフリー・ディーヴァーのリンカーン・ライム・シリーズ第3作です。まだハードカバーでしか出版されていないので図書館を利用。
次作、次々作の「石の猿」「魔術師(イリュージョニスト)」同様、ウェイティングした後、やっと借りられました。シリーズ第3作目ともなると、どうしてもマンネリ化、パターン化の弊害が避けられずあらが目につくものですが、この作品は上手にその轍を踏むのを免れています。
まず舞台設定。部屋から出るどころかベッドから離れられないというライムの設定が、どうしても話が単一的になってしまう原因の一つなのですが、 このライムがNYを離れてカロライナへ遠出します。もちろん重要な理由があるのですが、それは物語の中でライムのモノローグの心情として語られます。
ところが、出先で殺人+誘拐事件が起こって、計らずも時限協力することになってしまいます。もちろんパートナーのアメリアも一緒。 日常使い慣れている分析機材も無く、有能な操作助手も不足、土地勘がまったくないところでさすがのライムも「陸に上がった魚」状態。
しかし田舎バージョンのせいか、殺人誘拐犯人も未成年、これまでのような凶悪犯でもなさそうです。ギャレットは湿原に住んでいる"昆虫少年"とあだ名される16歳の少年で、 周囲からは知能も低いと思われているのですが、並々ならぬ昆虫生態系の知識を利用してスズメバチの巣のブービートラップを仕掛けたり、考えようによっては凶悪危険な犯罪人です。 彼が女子学生を誘拐しその現場に居合わせた青年を殺して湿原に逃げ込んだあとをライムとその手足となるサックスが追います。少年の愛読していた昆虫図鑑を読みながら 少年が昆虫の生態からヒントを得ながら行動してるのを見破って分厚い本のまだ半ばも行かないうちにあっけなく犯人逮捕。
さすがのディーヴァーも、この作品は小粒か? 一瞬そう疑いましたが、いや、さにあらずで、これからが大波乱。 少年の有罪を信じられないアメリアが勾留中の少年と逃亡、分析証拠の論理性を信じるライムが心ならずも二人を追うという構図になってしまいます。お互いの考えることがわかる二人の知恵比べ的な展開。その後、地元警察に包囲されたアメリアは絶体絶命のピンチに陥ります。
それも一時的なピンチではなく、偶発的な事故が原因で今後のアメリアの一生に関わる後戻りのできない行為をしてしまいます。
しかし、ディーバーの真骨頂はどんでん返し。しかもライム・シリーズ、まだ続編がある・・・・・・てことは、アメリアはこのピンチを何とか切り抜けるんだ、などと邪道で期待を抱きながら読み進むうちに、ああ、またしても例のどんでん返しに や ら れ た! それも最後の最後、数ページになってもまだひっくり返すんだから。
ディーヴァーのストーリー展開のやり方は強引で無理が多すぎると手厳しく評価する人もいるけれど、このスリル、はらはらどきどきのどんでん返しの妙は、たっぷり、有り余る読者へのサービス精神なのでしょうか。 最後にはライムが○○○?とまで思わるような描写。信じたわけではありませんが、やはり不安感を抱きながら物語を追いました。
このようにゆっくりしたペースの前半にはじっくり湿潤な南部を舞台に昆虫少年ギャレットの描写を多用して、いつもとは違った物語の進捗スピードを読者に体感させながら、後半で一気に以前にも優る 急展開を用意して、ややストレスを感じ出した読者を目の回るようなローラーコースターに乗せるところ、芸達者さを再認識しました。
しかもギャレットにはどこか"ブルー・ノーウェア"のワイアットと相通じるマニアックさがあったり、ライムの会話中に"静寂の叫び"に登場したポター捜査官の名がでたり、ディーヴァー・ファンを にんまりさせる「かくし技」付きの大サービスでした。
静寂の叫び ジェフリー・ディーヴァー

 ディーヴァーの作品の中でも傑作の名の高い作品。
この作品が紹介されると一躍日本にディーヴァー・ファンが増えたそうである。リンカーン・ライムのようなシリーズ物ではないが後の諸作品に開花するディーヴァーらしさの萌芽をすべて備えた
読み応えのある一作になっている。
ディーヴァーの作品の中でも傑作の名の高い作品。
この作品が紹介されると一躍日本にディーヴァー・ファンが増えたそうである。リンカーン・ライムのようなシリーズ物ではないが後の諸作品に開花するディーヴァーらしさの萌芽をすべて備えた
読み応えのある一作になっている。刑務所を脱獄した3人組の凶悪犯が通り合わせた聾学校の女子生徒と教師8人を人質に、食肉工場の廃工に立て籠もる。人質救出にあたるのがFBIの危機管理チーム交渉担当のスペシャリスト、ポター。ライム、キンケイドらに 比べると事件解決に繋がる神業のような能力を持っているようには見えない。50代の腹の出た平凡な男。しかし彼こそは難しい人質事件を何件も解決に導いた粘り強く不屈の精神を持っている男だ。
ところが、さしもの彼も今回の事件には眉を顰める。人質になったのは一人の健常者の教師を除いてすべて聴覚障害を持つ少女たち。しかも主犯格の男は交渉にあたって微塵の動揺もなく「見せしめ」の ために女生徒を一人解放すると見せかけて平然と背後から射殺する冷血さを見せる。しかもその本来の目的は不明である。
ポター始めFBIの精鋭交渉担当官たちが対策を取る一方で、管轄意識を振りかざし実力介入への意欲を満々と 示す州のHRU(人質救助部隊)、次回の選挙がらみの売名からか勝手に人質志願する州の法務次官補、閉め出されたのを根に持ってなんとか忍び込んで中継映像を放送しようとするスクープ狙いの マスコミ関係者、そういった個々の思惑で動く予想外の障害が、ポターたちの仕事を益々困難な物にしていく。
物語は多角的な視点から語られる。ある時はポターの心理が、ある時は人質の研修教師メラニーの目を通して、ある時は州警察の刑事の思惑を、またある時はHRUの隊長の本音を、次々にその当人に 語らせていく。もちろんストーリー上で大きなどんでん返しになるあることを秘するために主犯の心は詳細には語られない。それはやむを得ないことではある。
非常に目新しく、しかもリアリティを感じたのは、人質交渉人のあり方が詳細に述べられていること────犯人を理解せよ、犯人の話を聞け、同調せよ、しかし相手を優位に立たせてはいけない、最終的には犯人が次に何を言うかまで 予測できるほどに相手を理解し思考パターンの先を読み、自然に人質に害を与えたり殺したりしても無益である、人質を解放して降伏するのが自分にとって最良の選択であると自発的に思わせることが 目標である────明確にそういった行動基盤を持っているにもかかわらず、常に自分を検証しチェックをしていないと、ややもすれば犯人に心理的に同調し共感を抱いてしまうストックホルム症候群に 交渉人自らが落ち込んでしまう、そういった危険性も孕んでいる実に困難な交渉人には強靱な意志と鉄壁のバランス感覚が要求されるということなど、本物の現場のマニュアルを読んでいるような気分になる。 さらに、もう一つ新鮮だったのは聴力障害者たちのコミュニケーション方にかなり踏み込んで描写している点である。外側から窺い知れない生来の聾者と中途聾者との確執、読唇術の是非、音を聴覚には 頼らずに震動として感じる生気に満ちた描写など細かい資料収集とリサーチの成果を作品上で披露してくれている。
最後近くでポターが無力感を感じる大きな転機がある。それまでの自分の積み上げてきた方法がまったくの無力だったことを知らされる場面。しかしそろそろディーヴァーの自家薬籠中の「意表を突く どんでん返し」に慣れてきたのか、展開に無理があると疑問を持ったところが実はどんでん返しの布石だったことに気づいて、われながら嬉しかった。しかし、最後の最後の展開には思いも寄らなかった ので、あっけにとられたまま、それでも大いに余韻を残して、またしても「やられた」と思わされながら物語は悠々と終わってしまった。
青い虚空 ジェフリー・ディーヴァー
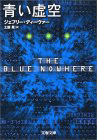 男が二人いる。共に天才的なセンスでコンピュータプログラムのコードを書き、ともに「アクセス騎士団」というハッカー・ギャング・グループを結成し
ネットの海にダイブして堅固なセキュリティを誇る政府機関や巨大産業にハッキングをした。しかし二人の道は別れた。
男が二人いる。共に天才的なセンスでコンピュータプログラムのコードを書き、ともに「アクセス騎士団」というハッカー・ギャング・グループを結成し
ネットの海にダイブして堅固なセキュリティを誇る政府機関や巨大産業にハッキングをした。しかし二人の道は別れた。一人はその驚異的なスキルを実害のある目的には決して使わなかった。もう一人は嗜虐的な性格から、ヴァーチャルのゲームをリアル・ワールドのゲームに混同し始めた。危惧を抱いた男はもう一人の書いた他人の死を招くプログラムを無力化 するワクチンを流すと共にその男の犯罪性を立証するプログラムのコピーとアドレスを警察に送付する。かくしてその男の犯罪は未然に防ぐことができ、男は逮捕された。
数年後、グループのNo.2だったジレットは国防総省の暗号化ソフトを破ってハッキングしたかどで服役中であったが、矯正施設からカリフォルニア州警察のコンピューター犯罪課へ協力を条件に一時的に移される。残虐で奇妙な連続殺人事件の捜査のためである。犯人は被害者の コンピューターに痕跡も残さず入り込みその家族、仕事、私生活とあらゆる情報を手にして、しかも被害者の知人を装って疑念を抱かせないように近づき、そしてナイフで心臓を刺すという まさに「魔術師」のような手並みを持っている。この犯人に対抗できるコンピューターのスキルを持っている「魔術師(ウィザード)」はジレット以外にいないのだ。
しかし事態はもっと重大だった。いかなるコンピュータにも 痕跡を残さず侵入し、必要な情報を確実にハックする「バックドア」と呼ばれるプログラムを悪用すれば世界の政治・経済・安全保障に考えられないような打撃を加えることができるのだ。 そしてそれを操っているのが人格崩壊をきたしている"フェイト"のHNを持つ男─── "ヴァレーマン"ことジレットの元の仲間でNo.1だったホロウェイという男だった。そして彼こそが、かつてジレットが 犯罪を未然に阻止した男なのだ。ホロウェイはジレットに復讐を誓っている。
かくしてネット上の二人の対決が始まる。お互いに相手の手の内を知り尽くしながら、現実世界では会ったことも声を聞いたこともない。二人が闘うのは"Blue Nowhere"=青い虚空─────コンピューターの内部に広がるバーチャル空間、それは縦横に電気信号が疾駆して現実の世界を支配する力をも持つ電脳空間。
原書ペーパーバックの書評には 21st century version of the "Gunfight at the O.K. Corral,"(OK牧場の決闘の21世紀版)と書かれているようにこの二人の対決を軸にして被害者、警察の人間、 ハッカー様々な人間が入り乱れる。さらにディーヴァーの真骨頂、輻輳するプロット、二転、三転、四転、五転してまだ真相がつかめない緊張と興奮。フェイトの共犯者は誰か?ジレットの 真の目的は何か? 警察内の裏切り者は誰か? 最後まで息をつかせないサスペンスの連続。
ディーヴァーの筆は私たちが絵空事と考えがちなBlueNowhere(ブルー・ノーウェア=青い虚空)に暗躍するハッカーたちの姿を生き生き 描き出し、実に身近に感じさせてくれる。そして「できるね・・・・・・ほとんどの犯罪はコンピューターでできる。コンピューターを使って人殺しだってやれる」という記述が空恐ろしいほど現実の物として 感じられる一方、「一度でもブルー・ノーウェアへ入ったら真の意味でリアル・ワールドへ戻ってくることは不可能なのだ」という蠱惑的な言葉もまた実感として感じられる恐ろしさも併せ持っている。
他に物語の厚みを広げているのは、殺人課の刑事ビショップとジレットの交流。まったくコンピューター音痴で最初は懐疑の目でジレットを見ていたビショップが次第に信頼していくさま、また 「社会工学」(ソーシャル・エンジニアリング)と称して、偽りの自分しか見せていなかったジレットがビショップに始めておのれを語るところまで心を開いていくさま、そしてフェイトの阻止 という同じ目的のために闘う過程でまったく違うキャラの二人に友情が育っていく様子は読んでいても楽しい部分である。コンピューターおたくのジレットの描写も真に迫っていて思わずにんまりさせられる。
コフィン・ダンサー ジェフリー・ディーヴァー
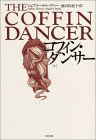
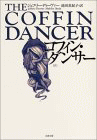 ジェフェリー・ディーヴァーのリンカーン・ライム=シリーズ第2作の文庫化です。
ジェフェリー・ディーヴァーのリンカーン・ライム=シリーズ第2作の文庫化です。リンカーン・ライムと言えば第1作「ボーン・コレクター」がデンゼル・ワシントンとアンジェリーナ・ジョリーのコンビで映画化されて有名です。
リンカーンは元ニューヨーク市警科学捜査部長、現場の鑑識中に受けた事故の外傷による頸椎損傷で四肢麻痺の障害者、現在は市警からは退いているものの難航する犯罪捜査に顧問として 参加、驚くべき知識と記憶力、天才的なひらめきと緻密な捜査、分析力で犯罪者の特定に努めます。これほどの能力を持ちながら自宅のベッドを一歩も離れられないリンカーンに代わって、実際の 犯罪現場に赴き精査して証拠集めをするのが、ニューヨーク市警の巡査からリンカーンに認められて助手的存在になったアメリア。まさに頭脳と手足、理性と情熱という名コンビです
「ボーン・コレクター」では四肢麻痺と自律神経の発作で尊厳死まで考えていたリンカーンが、アメリアという手足を得て、"ボーン・コレクター"と渾名された連続殺人犯を追いつめる、その過程で 生きる意欲を新たに持ち、アメリアとの間にも暖かい信頼関係が芽生えるという大筋でした。本作「コフィン・ダンサー」はその1年半ほど後の設定です。
一人の武器商人の証拠隠しを目撃した3人の証人の命を"コフィン・ダンサー"という殺し屋が狙っている、大陪審まで45時間余り、その間にダンサーが3人を殺すかそれともライムがダンサーの 裏をかいて逮捕に漕ぎ着けるか、顔も声も知らない二人が知恵の限りをつくし相手を阻止すべく死闘します。
意表をつくどんでん返し、それも一度や二度ではなく。それに多くの登場人物がそれぞれに個性的で暖かい目で描かれているのも楽しめる一因。たとえば命を狙われる女性パイロット一人を とっても彼女の「空を飛ぶ」充実感が彼女の目を通して伝わってきます。ダンサーとおぼしき殺し屋の自分との会話が一人称で克明に記されてたり、逆に体の自由の利かないライムの焦燥が 手に取るようにわかったりする描写の達者さ。
爆弾が仕掛けられていることも知らずにいる人々、仮面を脱いだ殺し屋が後ろから迫っているのに気づかない人々、狙撃地を密かに変えているのに目くらましに かかっている人々、その姿をやきもきしながらまさに無力に手をこまねいて、しかも先を知らねばならないために半ば脅迫的に読まないではいられない読者=このわたし、すべての要素が一体になって 物語の終局に向かって一気に高まっていきます。
まさにサスペンスものの読書の醍醐味であり、アダージョ楽章にはライムとアメリアのお互いに惹かれ会う気持ちが心地よく響いて、コーダへ続くあたり、読者冥利につきると思いました。
第3作「エンプティー・チェアー」、第4作「石の猿」、第5作「魔術師(イリュージョニスト)」もこの10月に刊行されました。たのしみはまだまだ続きます。
幽霊第五惑星 ロバート・シェクリー
復刻版第二弾です。ロバート・シェクリーといえば短編の名手。確かに「不死販売株式会社」とか「標的ナンバー10」などの長編もありますが、やっぱり「人間の手がまだ触れない」「宇宙市民」「地球巡礼「明日をこえる旅」「無限がいっぱい」など 短編こそシェクリイの活躍の場だったように思えます。シェクリイなら何でもお気に入りというわけではありませんし、アイディアやストーリーもどちらかというとトラディッショナルな(今で言うと古風な)感じがしますが、 その多彩なバリエーション、個々の作品が一線を越えて品の良さを保っていることなどが半世紀近く前の作品でも時代にあわない不自然さを感じることなく楽しんで読み返すことができる理由でしょうか。
この「幽霊第五惑星」は AAAエース惑星消毒サービス会社シリーズの1作です。SFマガジンに掲載されましたが、その後短編集に収録されることもなく、話題にもならなかった作品ですが、わたしとしてはかなり気に入っている作品です。 アイディアは、まあどこにでもある話です。植民者はみな惨殺されてしまう星───やや!スプラッタものか?幽霊の出る星───ホラーもの? 人間の潜在意識が恐ろしい実在のものになるんだって───おお、やっとSFらしくなってきた。 こんな具合です。でもわたしが長らく忘れられなかったのは潜在意識の最奥に潜んでいたのが子供のころの恐ろしい想像上の怪物、主人公二人が子供に戻って怪物をやっつけようとするそのプロセスがとても 面白いし、共感できたからだと思います。人間誰でも子供のころのいわれのない恐怖、たとえば暗闇とか、お化けとか……そういうったものを懐かしく思い出させてくれる「ほっとする後味」を 感じさせてくれる小品です。この作品を始め多数の翻訳、著作をされた矢野 徹氏が最近鬼籍に入られました。年月を感じます。 ──→ 幽霊第五惑星(内容紹介)へ
月の犬 アーサー・C・クラーク
たいして有名でもない小説、それも特に雑誌に掲載された短編などを記憶を元に長い年月が経ってから探し出すのは並大抵のことではありません。正直言ってわたしは記憶力がいい方ではないと自覚しているうえに とみに最近は"まだら惚け"が始まったのか、以前覚えていた書名、人名などがぽろぽろ脳細胞からこぼれ落ちていくような危機感を覚えています。ところがずっと以前に読んで、内容の一部、極端な場合には最後のオチの一言しか覚えていない作品を、無性にもう一度読みたいという衝動に駆られる事があります。長い年月温めてきたのだから、他の人はいざ知らず、自分にとって何か 大切なものがあるに違いない、それを再確認してみたい、その誘いに耐えかねて、未整理の蔵書をひっくり返してやっと一つ発見したのがこの短編です。
SFマガジン1968年6月号掲載……この年代だけでしっかり年がばれそうなのですが、これはわたしがまだSFのなんたるかも知らないころ、ただ未知の世界に精一杯背伸びをして手に取るのも恐ろしいような気分で 書店で躊躇したあげくに買ったごくごく初期のSFマガジンです。それこそ表表紙から裏表紙まで舐めるように読んだうちの1冊です
主人公の"わたし"とシェパードの"ライカ"との物語。子犬の時に拾って離れられぬ絆ができる、しかし"わたし"が月に赴任するにあたってペットの持ち込みは許されなかったので、ついにライカを人手にゆだねて別れる。 時を経ずしてライカは死ぬ。それから5年、ある事件が元でわたしはライカのことを思い出し心から懐かしく思い涙する─────ストーリーはこれだけ。何も取り立てて新奇な着想も印象深いシーンもなさそうに見えます。
では、一体何がわたしの心に引っかかっていたかというと、"人の心は時として不思議な働きをする。潜在意識が、その人にどういう刺激を与えたら一番速く反応するか、それを記憶していて 当人も気づかないうちに最も効果的で最も心の琴線に共鳴する信号を出す"というコンセプトでした。以前に大地震が起こるのを察知して狂ったように吠えて自分に危機を教えてくれた犬。 その犬が夢の中に現れて同じように吠える、それは自分の潜在意識がその犬の姿と声によって自分が一番速く「地震」と関連づけて覚醒すると知っていたから。合理的な説明があって、後、その犬が 自分にとってそれほど大切なものであった、それはとりもなおさずその犬が幽冥の境から自分を救ってくれたのだと、自分でも封印していた犬への思いをほとばしらせる、記述が淡々と しているだけに最後の一節で溜めに溜められたしみじみとした感情の高まりをわがことのように体験した気分になりました。
長年気になっていただけに今読み返しても同じような感慨をもてたことに安堵しています。
ps. アーサー・C・クラーク 「月の犬」で検索してもヒットしないので現在読むことはできないと思います。内容紹介のファイルを作りました。ご興味のある方はご一読下さい。 ──→月の犬(内容紹介)へ
壁の中 シオドア・コグスウェル
先日見た映画 "The Village"の基本的なアイデアについてネット上の友人と話していて、いくつか似ているものに話が及びました。一つは SFの大御所、レイ・ブラッドベリの短編集「10月はたそがれの国」所載の"びっくり箱"、もう一つはシオドア・R・コグスウェルの"壁の中"という短編です。 前者は萩尾望都さんによって漫画化もされているので比較的目にとまりやすいのですが、後者は所載の本が絶版で入手しにくいこともあってあまり知られていないのが実情です。寡作な作家でもある一作によって文学史に名を残す、そういう例を目にすることがありますが、コグスウェルもそういった一人です。「壁の中」は往年の名作短編集には頻繁に顔を出していた忘れがたい佳作といえます。
主人公ポージーは13歳の少年、世界は周囲を高い壁で取り巻かれている。その壁を越えられるものは誰もいない。そもそも壁を越えようと思うものもいない。ポージー除いては。 魔法と精神の力が当たり前の世界。人は何世代もの間絶えざる努力を払って心で物を宙に浮かし動かし、心で人と話をする力を培ってきた。呪文を唱えれば箒である程度の高さまでは空を飛bu 事もできる、ただし壁の高さには達しないが。
ポージーには父がいない。彼がまだ小さい頃にタブーを犯して<外>からきた<黒い人>に拉致されて行方不明になっている。タブーとは<機械>を作ったこと、それも<飛ぶ機械>を。 ポージーはこの事実を知らない。学校では練金学にも占星術にも身が入らない、頭の中には、空を飛んでいる鷲のように魔法が使えなくても飛ぶことができないか、その手だてはないか、そのことばかり。
高等魔法の本で粘土の鳥を飛ばそうとするが失敗する。粘土は粘土に過ぎない、飛ぶためには目的に見合った合理的な道具が要る事を痛感したポージーは先生の叱責や叔父の心配もよそに 密かに<飛ぶ機械>を作り始める。魔法の箒を推力にして初めて上昇気流を捕らえて、今まで登ったことのない高みに達する。その高揚! しかし壁はあまりに高い。越えるためには強い上昇気流に達するまで上れる大人用の箒がもらえる14歳の誕生日まで待たなければならない。その日を指折り数えるポージー。
しかし事態は深刻になりつつあった。従兄の悪意に充ちた密告でポージーの飛行機械の存在が先生の耳に入り、ついに外界から<黒い人>が彼を連れに来るという。狼狽する叔父、叔母。 箒をもらえなかったポージーは失意の中にも従兄の挑発にのって、飛行機械で少年たちのたまり場へ飛び出す。子供っぽい優越感とたわいもない口げんかから、気流を逃したポージーの 飛行機械が従兄の手で壊されかかる。
意を決したポージーはこれが最初で最後と強い上昇気流にのって壁の上を目指す。壊れそうにはためく飛行機械を操りながらポージーは壁の向こうをかいま見る。 墜落しながらもやっと壁の上に着陸したポージーに曙光の中で上空から襲いかかってきたのは<黒い人>だった……
「壁」や「魔法」や「黒い人」などのガジェットに気を奪われてしまいますが、一番魅了されたのはやはり壁に囲まれて充足している世界という世界観。この設定で読者は何の疑問も抱かずに 無理なくファンタジーの世界へ没入します。魔法も呪文もOK。その一方、いわば私たちの合理主義的心性を持つポージーにも違和感を抱かずに共感できます。空気抵抗や揚力や推力 といった物理学が支配する実体世界は私たちに属する物ですから、ポージーの挫折の苦悩や成功の喜びをわがこととして共体験できます。
「ヴィレッジ」「びっくり箱」にも共通するのがこの共体験なのだと思われます。知らず知らずのうちに自然にその設定に入り込み共に訝しく思い、共に恐怖を感じ、共に勇気を奮い起こす。 そして共に驚愕の事実を知る……。
「壁の中」における"壁"、「ヴィレッジ」における"禁忌の森"、「びっくり箱」における"家"、これらはすべて外界から自分たちを区別する境界であり、その中に留まっている限り人は 安全を保証されています。世界はその中で完結して充足しており、内部の人はその中で自己を磨くことができ、望みをかなえ幸福を追求することができます。しかしある人々にはそれは隔絶を意味し、いやが上にも 「外」を意識させます。もちろんこの3作に登場する人々が「外」を意識して「外」へ出ることを画策する動機はまちまちです。単に純粋な好奇心から外をうかがい知りたいポージー。期せずして外へ 出て初めて自分が囲いの中にいたことを知る「びっくり箱」、已むに已まれぬ必要から死をも覚悟して森に踏みいる「ヴィレッジ」。 しかしそのすべてが「外」へでたことによって今までの世界観が180度転換する現実に直面する事になります。
現実を知った結果の是非はさておいて、ここに登場する庇護・保護の究極の形態である「囲い・檻」は機能上必然的に 自由を奪い束縛をもたらします。庇護・保護を計った先人たち、親、第一世代はそれが最上の方法だと信じて境界を作るのですが、生まれながらに境界が存在する世界に育ち成人していく 子孫、子供、第二、第三世代にとって果たしてそれが最上最善の方法であるかは誰も断定できないのです。選択はおのおのによってなされなければならないのです。そして選択を行うためには 過酷な現実を知らなければならないし知ったことで傷つきもするし無知でいた純粋な世界に戻ることもできません。それでも、そのジレンマのからくりを実感していなくても囲いの中にいる人間は 囲いの外を意識し、知りたい、出てみたいという衝動を抑えることはできないでしょう。自分の道は自分が選び取る───この言い古された陳腐な言葉の持つ峻厳である意味残酷でもある意味が改めて 思われます。
幸いなことにポージーは壁を越えることができます。そして新しい世界を発見します。そして読者の心をくすぐるような最後の一節もあります。実際の所、この短編がわたしのお気に入りの座を占めているのは この一言がいつも笑いを誘ってくれるからなのです。──→壁の中(内容紹介)へ
ダーリンは外国人 1,2 小栗左多里

 今、密かなブームになっているこの本、読み終わる頃には、「うちにも一人トニーが欲しい」と
口走ってしまうこと請け合いです。外国人との国際結婚というと、この節あまり珍しくも無くなってきましたが、「じゃ、お前やるか?」といわれると「ちょ、ちょっと……」と引いてしまうのが落ちです。
それでもって、完全に言葉が通じなくて充分なコミュニケーションがとれるのだろうか、とか友人には面白いけれど、終生の伴侶には二の足を踏むと、もごもごいいわけをしたり。
今、密かなブームになっているこの本、読み終わる頃には、「うちにも一人トニーが欲しい」と
口走ってしまうこと請け合いです。外国人との国際結婚というと、この節あまり珍しくも無くなってきましたが、「じゃ、お前やるか?」といわれると「ちょ、ちょっと……」と引いてしまうのが落ちです。
それでもって、完全に言葉が通じなくて充分なコミュニケーションがとれるのだろうか、とか友人には面白いけれど、終生の伴侶には二の足を踏むと、もごもごいいわけをしたり。でも、分かり合えないって、これは日本人同士だっていくらでもあり得ることなんですね。外国人だから、日本人同士だから、なんて画一的に分類できることじゃないんですね。むしろ、相手個人がどのような考え方をしてどのような感じ方をして、どのように他へ働きかけるか、それを理解しあうことが一番重要であるんですよね。
この本はそんなことを期せずして、面白おかしくわからせてくれます。漫画と文字が適当に入り交じって漫画好きにも活字好きにも抵抗無く受け入れられる、お得な本です。
実は"ダーリン"ことトニー・ラズロさんは英字新聞ST(スチューデント・タイムズ)のバックの"オピニオン" のページの複数執筆者のお一人。彼の英文は、まさにこの本のトニー、そのものが書いた!と言うような文章。 一筋縄ではいかない修辞法や、凝った言い回し、豊かな知識と飽くなき探求心がわき出るような文章。つまり高校生にはちょいと難しいかな?という文章。
以前から新聞は読んでいたので、この本を読んだ途端に、「ああ、あのラズロさんだ!」と叫んでしまいました。そしてちょいと神経質で難しいそうな髭面のハンサムさんが、ずっと身近に感じられるようになりました。
小栗さんとの珍問答も端から見ると奇矯な行動も、彼なりに一貫していて、それが今までの彼の書いた文章から知った彼の考え方と一致しています。
何も異なった文化の中で無理に自分を歪めて文化に埋没してしまうのが順応なのではないことを、実生活に即して、そして何よりも実生活を楽しみながらソフトタッチで教えてくれる、「赤い」(*注)読後感を味わえる本でした。
*注 「赤い」はラズロさんによると「最高!」の表現らしい
↑ ページトップへ