黒祠の島 小野不由美
 12国記以来久しぶりに小野不由美の小説を読みました。
現実離れした事件が起こるには現実から離れた舞台が必要になります。
そこで起こる失踪と殺人事件は一見単なる猟奇殺人に見えます。しかし真相を知るにつれて、事件はその裏に特定の共同幻想を持つ人々の住む限定された地域でしか起きない特定の意味を持つ物になります。
12国記以来久しぶりに小野不由美の小説を読みました。
現実離れした事件が起こるには現実から離れた舞台が必要になります。
そこで起こる失踪と殺人事件は一見単なる猟奇殺人に見えます。しかし真相を知るにつれて、事件はその裏に特定の共同幻想を持つ人々の住む限定された地域でしか起きない特定の意味を持つ物になります。
それは外の人間の「常識」では了解不能のものです。 外界の人間がそこに闖入し、事件を解明しようとすると有形無形の妨害が始まります。それに負けて解明を諦めれば、殺人事件どころか、殺された人間のそもそもの存在すら抹消されてしまうのです。 友人を追って島へ渡った男は島民の反発と妨害に合いながら、徐々に隠された過去の殺人事件と現在のそれとの関連を解き、慣習に隠れて行われた凶事のうらにある生々しい人間の嫉妬、恨み、欲を暴いて、最後に伝説の中にしかいないと思われた「鬼」の正体を知るのです。伝奇的でありながらホラーでもあり、本格推理の謎解きのおもしろさも併せ持つ、そういう興奮を覚えた一冊でした。
夜の回帰線 マイケル・グルーバー

 読了。ふ〜〜、楽しかった、怖かった、興奮した。
久しぶりに読み終わるまで手放せなくて、行くところ行くところ持参して読みました。
でも、気を入れて読まないと大事な情報を見落としそうで、幾度か確認の読み返しなんかもしました。
読了。ふ〜〜、楽しかった、怖かった、興奮した。
久しぶりに読み終わるまで手放せなくて、行くところ行くところ持参して読みました。
でも、気を入れて読まないと大事な情報を見落としそうで、幾度か確認の読み返しなんかもしました。
主人公の独白文体と何年か前の(実は事件の発端になっている)出来事を書いた日記と、リアルタイムで実際に起きている事件を第3者の目で書いた3つの文章文体が錯綜して、読んでいる方まで知らず知らずのうちに何が現実なのか、それともすべてが幻覚なのかわからなくなってだれが悪で誰が正義なのかも曖昧になり…… とにかく最後の1ページまで気を緩めることなく読ませられました。
扱っているのがブードゥーをはじめ、アフリカの土着信仰、シベリアの幻の民族の原始宗教など。わたしたちに全く知識も縁もない宗教、それに関わった女性と夫の間の追跡と抹殺を目的とする襲撃の物語なのですが、まやかしだ、幻覚だと合理的に切り捨ててしまえないところに背筋が寒くなるような怖さがあります。
クリスマスのフロスト R.D.ウィングフィールド
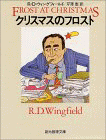 しばらくミステリーから遠ざかっていたのですがおもしろさに一気に読みました。これがウィングフィールドのデビュー作とは思えないプロットの進め方。複数の事件が輻輳しているようで、結局最終的に関連性が明らかになって行って一つにまとまっていく醍醐味。それにフロスト警部という、どうしようもないほどだらでドジなキャラ。いい加減さは天下一品のくせに他人に人一倍暖かい思いやりをここぞとうところで見せる秘めたキャラに惚れました。
しばらくミステリーから遠ざかっていたのですがおもしろさに一気に読みました。これがウィングフィールドのデビュー作とは思えないプロットの進め方。複数の事件が輻輳しているようで、結局最終的に関連性が明らかになって行って一つにまとまっていく醍醐味。それにフロスト警部という、どうしようもないほどだらでドジなキャラ。いい加減さは天下一品のくせに他人に人一倍暖かい思いやりをここぞとうところで見せる秘めたキャラに惚れました。
もっとも、この口は悪いし強請、たかりまがいのことも平気でやる憎めない小悪党さがとっておきの魅力なのですが。 小説の構成も秀逸。冒頭は何の話か全くわからない状態でフロストの窮地が描かれるところから始まり、時間を遡って事件の発端から時系列で事件の発展、顛末と様々な興味深い人物を絡めながら展開していくところは上質の映画かドラマを見ているような視覚的効果を与えてくれます。またまたフロストの続編をよまなくっちゃ。
ミュータント ルイス・パジェット
これは早川銀背だけで出ていると思います。ハヤカワでも再版文庫化されていない、かなりマイナーな作品です。 ルイス・パジェットは聞き慣れない名前ですが、往年の名手、ヘンリー・カットナーの別名です。カットナーはC.L.ムーアのだんな。早くに亡くなりましたがSF、ミステリー、ファンタジー、怪奇小説など多岐に渡る種々の作品を残しています。「ミュータント」はA.E.ヴォートの「スラン」と比較されるミュータントテーマの傑作(私はそう思うのですが)5編の短編からなっていて、ある男の回想形式で、テレパシー能力を持つミュータントが核戦争後に現れてから、ノン・テレパスとの確執、 ミュータントの中での狂信的過激派パラノイドとの見えざる闘い、その200年に及ぶ歴史を書いたものです。
短編集なので大きなストーリー的な盛り上がりには欠け、プロットも詰めが甘いところはあるのですが、細やかな心理描写や、テレパスならではの苦悩、テレパスの中で更にパラノイアと闘うために唯一の慰撫である仲間との精神融合の悦楽から自ら身を引いたミュートたちの孤独、などなど、読む者を引きつける力を持っています。
再読するに至ったきっかけは、この短編がそれぞれ「笛吹の子」「三匹のめくらの鼠」「ビロードを着た乞食」「獅子と一角獣」「ハンプティ・ダンプティ」と題されていて、最初に読んだとき(中学生でした)に何かはわからないなりに、妙に心に残ったこと、後にそれぞれがマザー・グースの歌のタイトルであることなど知って、それらが単なる「タイトル」であるだけでなく、欧米文化を持つ人には、また別の隠喩が直裁的に感じられるのだと気づきました。 日本人にはなかなか理解できない、欧米文化の底流にある共通意識の存在を最初に感じた作品でもありました。
グリフィンの年 D.W.ジョーンズ
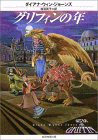 久々にDWJ(ダイアナ・ウィン・ジョーンズ)の邦訳を読みました。
「ダークホルムの闇の君」の続編「グリフィンの年」です。
久々にDWJ(ダイアナ・ウィン・ジョーンズ)の邦訳を読みました。
「ダークホルムの闇の君」の続編「グリフィンの年」です。正編に優るとも劣らぬ面白さでした。ただし今回の舞台はほとんどが魔法大学内なのでスケールはやや小振り。 しかし新しいキャラクター、新入学生の子供達が一癖二癖もあるくせ者揃いです。
ダーク家のグリフィンの末娘エルダもその中の一人。前作でこちらの世界からの観光団を追い出すことに成功はしたものの、40年の荒廃の爪痕は大きく新しい魔術師を生み出す教育体制も回復不能なほどに混乱しています。 新入生は大学に新風をもたらすのか?それぞれの新入生にまつわる謎と、延びる脅威の手、どうやって危機を脱するのか? ダーク家の面々のその後は?
原作の出版の年に66歳になったDWJ、ますます脂ののった筆の滑りを見せます。楽しくて度肝を抜かれて、そのくせ和やかで微笑みたくなるような部分を随所にちりばめ、そして最後にいつもの大団円。話がわ〜〜〜っと収束して全てに説明が付いて全てが良し!!
至福の2日間を過ごしました。
妖魅変成夜話 岡野玲子
 岡野玲子さんといえば夢枕獏さん原作の「陰陽師」の漫画化、もしくは原作からまた違ったスピンオフを作り出すのに成功した人です。
岡野玲子さんといえば夢枕獏さん原作の「陰陽師」の漫画化、もしくは原作からまた違ったスピンオフを作り出すのに成功した人です。最初は取っつきにくかった作画も読み進むうちに、この絵、このキャラしかあり得ないと思い込むほどに妖しい魅力に取り付かれてしまいます。
さてその岡野さんの「妖魅変成夜話」がお勧めの一冊。腰帯に寄ればもう20万部突破と言うことでご存じの方も多いと思いますが、とにかくこれも軽く楽しいのです。中国の妖奇・神仙物語、「剪燈新話」や「聊斎志異」などを彷彿とさせて、それに一垂らしのコメディギャグと大量のかっこよさを混ぜ込んで、世にも奇態な物語の始まり、始まり…… その昔中国に李成譚という挙人がおり、試験にむけて旅をする途中にいろいろあって、幽霊の女の子に見初められるは、地方の都に出れば可愛い色子に惚れられて、挙げ句の果てにそれは白狐だったり。やっと仕官が叶ったと思いきや、士官先は極秘部隊――――の超常現象の調査・記録係――――X-ファイルの事務職だと思えばよろしい。そこの所長、いや上司は、龍玉将軍という安倍清明もかくやと思うほどの美形。この人は謎の多い人で巻を追うごとにその正体がだんだんわかってくるのですが、とにかくかっこよくて色気があって男気があって人情を解し、そして何より皮肉屋で人使いが荒いw
こうして田舎のぽっと出の李成譚は将軍の指示に従って今日は桂州明日は洞庭湖と東奔西走、妖怪に食われかけたり、美女の誘惑の虜になって精を吸われたりさんざんな目に遭いながら何とか生き延びております。 お話しの洒脱な面白さに加えて、毛筆で書かれた絵と水墨画技法を使った背景など独特の雰囲気も楽しめる要因だろうと思います。
陰陽師 「生成り姫」 「大極の巻」 夢枕獏

 前者は最初の短編集に所載してあった短編の長編化、後者は単行本。
前者は最初の短編集に所載してあった短編の長編化、後者は単行本。ともに夢枕節、面目躍如といったところか。陰陽師のスタイルともいうべきものが確立しました。短編集を重ねる毎に定着して来た感があります。多分作者も初めのうちはそれほど意識していなかったのかも知れませんが、文庫でいえば鳳凰ノ巻あたりから、語り口も話の導入、結末を同じパターンで統一されるようになって、それがまた実にいい効果をもたらしています。まず晴明と博雅が、土御門の清明の屋敷の荒れ庭を眺めながら季節の移ろいを語りながらほろほろと杯を交わすシーンから始まります。博雅の素直な心根が自然を新鮮な驚きの目で見る時、清明が博雅がいかに的確に「呪」の本質に迫る洞察を持っているかを語る……
問わず語りに話が進むうちに事件が始まり、「いこう」「うむ、いこう」と渦中に飛び込んでいくことになります。 そして一件が落着して、また二人が濡縁で花を、月を、雪を眺めながら一献酌み交わすところで終わります。 なんだかこのパターンが懐かしくて新刊が出ると矢も盾も堪らず読みに走るのが、これまたパターンになっています。
ハリー・ポッターとフェニックスの騎士団 J.K.ローリング
 「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」(仮題)原書、読了しました。
「ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団」(仮題)原書、読了しました。既刊の4冊と違って全く重く暗い話です。
それにもかかわらず面白い、先が読みたくて、後になるほど加速して読みました。
邦訳が出ていないので内容に触れてどこがどうと感想を書けないのが残念ですが、最初から言われていた「重要人物の死」は本当に結末近くなってから。それもあっけなく死んでしまいます。
その人物の死が大きな物語を動かす支点になるというより、そうい事態に至るのに、ハリーが無意識にとはいえ、自分を責めずにはいられないミスディレクションをしてしまうこと。それに気付いたハリーの自責の念、更にある人から告げられるハリーと旧敵の間にある宿命的な運命の絡み合い……
それを一旦聞いてしまったハリーにはもう心が芯から落ち着ける安逸の場はなくなってしまったと同じ。
暖かい陽光は差しても、楽しく笑いさざめく友達はいても、このハリーの運命を分かち合ってくれる人も、況や運命を軽くしてくれる人もいないのです。 5巻は悲劇的様相のまま終わりを迎えます。でも砂糖菓子のようなお子さまファンタジーから一皮むけた気がしたのも確か。他の多くの人々もそれぞれの生き方に従って新しい道を選んでいきます。
いつまでも楽しい面白い、だけに留まっていられないのはどのような作品についても同じですけどね。
影が重なる時 小松左京
小松左京の初期の中短編には忘れられないテイストのものがたくさんある。それこそ、湧くように出る多種多様なアイデアをメモ代わりに小説にしていると評した人もいるが、まさにその通りである。ちまちました市井の庶民生活の情趣を感じさせられる佳作から、希有壮大な宇宙の来し方行く末をほんの数頁に凝縮したもの、 しっとりと能舞台を見るような静謐さあふれる歴史物、果てはもう一歩踏み出せばお下品と揶揄される下世話物まで、それはそれは底の知れない知性と諧謔と表現の幅をどうして一人の人間が持てるのだろうと舌を巻いた覚えがある……今をさかのぼること何十年、小松左京と遭遇した中学生時代である。
さすがにここ何年かは再読していないので作品に中には記憶は数万光年の忘却の彼方へ飛翔してしまったものもあるが、いくつか、それこそ忘れようにも忘れられない印象を心に刻んだ作品もある。 その一つが"影が重なる時"。簡単にストーリーをおさらいしよう。
「私」はある地方中小都市に住む新聞記者、何の変哲もない平凡で何十年経っても大きな変化なんぞなさそうな町に住んでいる。ところが……ある日この町に住む人々の幽霊が出だす。出没するのではなく、幽霊と言う言い方も的を射ていないかも知れない。 つまり皆が皆自分のドッペルゲンガーを目撃する。その姿はある一点で時間が凍結したような瞬間の姿をしている。
「私」は新聞を小脇に大慌てで血相を変えて駆け出そうとしている。つき合っている彼女は頭にカーラーを巻いた部屋着姿で中空を見つめている、友人はトイレに幽霊がいて……このように皆自分の幽霊を見るのである。 ところがこの幽霊、他人には見えない。そこにいる、といわれても何もない空間があるだけ。手を伸ばしても何も触れる物もない。しかし……しかし当の本人はその空間に入れない、他人に手を引っ張られても自分の幻影が物理的に空間を占めているかのようにその空間に入り込めない。友人は気の毒にトイレを使えないので外で用足しをしている。
「私」は記者精神に目覚めてこの現象の原因を突き止めようと取材に走り回るが、そもそも他人には見えない幽霊であるので調査に来た学者も観測のしようがない、下手をすると集団ヒステリーではないかとまで言い出す始末。しかし「私」はある変化に気が付く。幻影が日ごとに鮮明になっていくのである。最初はぼんやりとしかみえなかった自分が質感を持ち、手に持っている新聞の文字が鮮明に見え、外光の陰影も見えるようになってくる。それと同時に自分の幽霊のあまりに必死の形相に胸騒ぎを止められない。
ところが不思議なことに幽霊の見えない人もいる、同僚の一人がどこにも自分の幽霊がいないので他の人間の騒ぎを疑いの目で見ている。もう一つ不可解にも車や機械のモーターが過負荷で焼き切れる事故が続く。 そして……運命の時刻は刻々と近づく。折しも「私」が幽霊の抱える鮮明になりつつある新聞を読み、半ば見える腕時計の針から時刻を割り出そうとし、その時刻にしては外から入ってくる光の方向がおかしいと気付いた時、まさにその瞬間に「私」は悟る。とてつもなく恐ろしい力を持った何かが迫ってくる。そしてその時この町にいた人間は皆死ぬ、この幽霊はまさにその未来の瞬間が張り付いた姿なのだ!
「私」は気が狂ったようにこの場から逃げ出そうと上着を掴んで走り出す。夕方だというのに外から強い光が射し込む。あっという間に「私」は「私」の幽霊の背中に突き当たってすっぽりとその中に入り込む。同様に彼女は強い光を訝しんで外を見上げる……その上空には軌道を離れた某国の(おそらく核弾頭搭載の)衛星(おそらく軍事目的の)が大気圏を突き破って、その都市に住む何万かの人々を一瞬にして無に帰す所であった。 蛇足ながら説明を。余りに大量のエネルギーが一瞬にして放出されたのでその時空が切り取られた形で位相を変えて何日か過去にあらわれたのだった。幽霊の見えなかった人はその時点にその町にいなかった人、つまり見えないと疑いをもった男はその日出張で町を離れていた。車や機械のようなその場にあった物は質量が重なって負荷が2倍になった。位相がずれているのでその瞬間まで同一質量を持つ物が同一空間を占められなかったというわけ。
なぜ半世紀近くも経ってこの小説を……と訝しむ向きもあるだろうが、最近ますますこの話に込められた恐ろしさが身に染みて感じられて来ている。 発表時は絵空事でしかなかった大空からの恐怖が急速に実体のある物として感じられるようになった。
ちなみに私の住んでいるT市は日本海側にある。近隣に原子力発電所もある。人工衛星ならぬNKからの中長距離ミサイルの到達圏内に位置している。NKの核開発疑惑が疑惑でなく既存の事実となりつつある今、国内経済に破綻をきたし国際社会から孤立し、悪の枢軸と名指してで非難されて、サダム政権が倒壊した今、NKが次の標的になる懸念が一段と強まった。
核抑止力にせよ報復攻撃を考えたら先制攻撃は出来ないというまことしやかな論理は失う物のない破れかぶれの狂信者にとって何の効力もない。自国の滅亡と共に世界を道連れに……という物騒な考えを持ちかねない人間がいないとも限らない。
ふと一人で風呂へ入っている時など恐ろしくなる、もし今上空から何かが近づきつつあったら…… 家族が離れて住むようになってもし誰か一人でも不慮の災難に巻き込まれたら……
もし風呂から上がってそこに後ろ向きの自分の姿が見えたら……
純粋に空想を駆使した疑似イベントの世界だったはずの話が、俄然わたしの前に実体のある恐怖を巻き起こす現実の話として現れてくる。そんな事は絶対にあり得ないと笑い飛ばせた昔が懐かしい。 あり得ないことが現実になった時、人は何に希望を見出すことができるのだろう。 疑似現実を現実に見せる時代を超えた小松左京氏の筆の冴えは確かに賞賛に値するが、現実が疑似現実に追いついてしまった現在をわたしは恐れの目で凝視している。
ダークホルムの闇の君 D.W.ジョーンズ
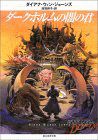 ダークは魔術師,家族は愛妻と息子と娘,グリフィンの娘と息子5人(5匹?5羽?),その他にダークの作った翼を持つ馬,同じくミニ翼で飛び回る豚,ひとなつっこい雌牛,透明の猫,野次る鵞鳥,肉食性!の羊……
ダークは魔術師,家族は愛妻と息子と娘,グリフィンの娘と息子5人(5匹?5羽?),その他にダークの作った翼を持つ馬,同じくミニ翼で飛び回る豚,ひとなつっこい雌牛,透明の猫,野次る鵞鳥,肉食性!の羊……いやはやこれだけでも何というにぎやかさ。
ダークの住む世界は魔法が当たり前の世界なのだが、単独にして最大の悩みの種は「別世界」から毎年訪れる「巡礼団」と称する観光団,どうもこの別世界というのがわれわれの世界らしいというのは冒頭で明らかになる。 何らかの呪いで――――どうも魔物との契約であるらしいのだが――――ダークの世界(こちらの世界)は,われわれの世界(あちらの世界)の搾取に甘んじている。
ディズニーを思わせる「チェズニー氏」の企業のテーマパークと化してはや40年になる。
毎年押し寄せる巡礼団=観光団,その「魔法と夢の冒険の体験ツァー」をほとんど無償で お膳立てするのがこちらの世界の義務。チェズニー氏の要求はますますエスカレートする一方。
世界を統べる「闇の君」を倒すクライマックスに至るまでに, ドラゴンに財宝を守らせる,魔女にヒントを出させる,飛ぶものに襲わせる,オプションで海賊の襲撃,または囚われて剣闘士にさせられる,が付く……闇エルフは出るわ,狼男も吸血鬼も,闇の軍隊も……
さて、今年の「闇の君」は……その役が当たると大変な目に遭うのでなり手がいない。そこで神殿の御神託でダークが「闇の君」息子のブレイドが先導魔術師に決められてしまう。 準備期間も無く大量の仕事を押しつけられ、そもそも動植物にかんする魔法が専門のダークは途方に暮れる。おまけに頼みの妻はなぜ冷たい態度,おまけに急に現れた超弩級のドラゴンの早とちりでダークは焼かれて半死半生。
すわ,家族の一大事と立ち上がった子供達ではあったが,5羽のグリフィンの性格が全部違うと来ている,人間の子供の使える魔法もばらばら。これじゃまとまりようも無く 内輪もめばかり。
これが前半、ここまで読み進めるのは一苦労だった。
まず取っつきが悪い。いきなり物語りの真ん中に放り出される感じ。進行になじんでキャラクターに 違和感を感じなくなるまでにかなりの忍耐力を要した。後になってD・W・ジョーンズの真骨頂、全てのストーリーラインが一つに収束して大団円を迎えるのだが,それに至る伏線やちょっとしたヒント,後になってあそこの記述が,と膝を打つところがほんの冒頭から書き込まれているのに気が付いた。
それを探すためにもう一度最初から読んでみた。巧妙な物である。気を付けて読めばわかると言うよりこれはもう作者の自己満足かといいたくなるような,ある意味大サービスである。 やはりこうでなくっちゃ。
この世界に現れる魔法は呪文を唱えたり摩訶不思議なモノをこね回して使うものではない。ちょうどわれわれが自転車の乗り方を学ぶようにやり方を 学べば,その能力があるものは使える力である。長年の隷従のうちにやり方が失われてしまった魔法もあれば、ダークの様にバイオテクノロジーまがいの説得力ある魔法を使う者もいる。
D・W・ジョーンズのファンタジーに共通していえることだが,どのように非現実的な設定をされても,それを非現実と感じさせないだけの筆力があるということである。 ハイファンタジーを読むといつも疎外感と完全に没入できない違和感を感じるが,彼女の作品に関しては,作品世界に迷いも疑いもなく沈潜できるという確信が持てる。だから好きなんだな,変に確信している。
余談だが彼女の「魔法使いハウルと火の悪魔」が「ハウルの動く城」(仮題)となってスタジオ・ジブリがアニメ化を進めているようだ。 宮崎さんがジョーンズのあのすてきなお話を壊さないように,そしてあの不思議感を十分に表現してくれることを願ってやまない。
魔女と暮らせば ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
 大魔法使いクレストマンシー;魔女と暮らせば
大魔法使いクレストマンシー;魔女と暮らせばこれが正式のタイトルです。ダイアナ・ウィン・ジョーンズの数ある作品の中で先頃改訳が出た作品。 以前「魔女集会通り26番地」(偕成社)として1984に出版されましたが絶版になっていました。
さきごろ翻訳が出た「私が幽霊だった時」「9年間の魔法」(東京創元社) についで、このクレストマンシー・シリーズ(4冊)も相次いで出版されることになったものです。
児童ものということで内容はずっとわかりやすいものですが、 構成が緻密な点ではひけを取りません。
この本では世界は単一ではなく系列と呼ばれるパラレルワールドからなり立っています。歴史の転換点毎に世界が分岐していって 世界の総数は第12系列まであるという設定です。ちなみに私たちの機械テクノロジーを持った世界はこの第12世界らしいですね。
さて、"クレストマンシー"とは飛び抜けて 強い力を持つ大魔法使いの称号で、クレストマンシーが年老いて世代交代する毎に次の時代のクレストマンシーの能力を持った者を探すことになります。
「魔女と暮らせば」の冒頭で、主人公の少年キャット(本名エリック)は船の事故で両親を亡くし、姉のグェンドリンと二人きりになります。 孤児になった二人は近所の魔術師達の世話になって暮らしていました。グェンドリンは将来有望な魔女で、自分でもそのことに自信満々、キャットはそんな姉に頼り切っていました。
やがて二人は、大魔法使いクレストマンシーの城に引き取らるのですが、「子供は魔法を使ってはいけない」といわれ、規律正しい暮らしをさせられることに我慢ができなくなった グェンドリンは、魔法で様々な嫌がらせをしたあげく、ある日突然姿を消してしまいます。
消えた姉の代わりに現れた、姉にそっくりのくせに「別の世界から来た別人」 と主張するジャネットという名の少女の面倒を見なければならなくなったキャットは、頭を抱えてしまいます。やがてグェンドリンの野望の大きさと、キャットにしてきたひどい仕打ちが明らかになる事件が起きます。
端から見ると、本当にこの人が大魔法使いなのかというくらいのんびりしたクレストマンシーをはじめ、周囲の人々が魔法を使うために立ち上がることになり、キャットも自分の本来の姿に 目覚めるのです。
既刊の「クリストファーの魔法の旅」はこの物語に先立つこと25年の物語、つまりクレストマンシーの子供時代の物語です。 読むならば「魔法の旅」から読む方をお勧めします。後日談に登場する人々の関係や、クレストマンシーの奇妙な癖や、隠された弱点などについて無理なく説明がなされていて シリーズものの持つ重層構造を楽しむことができます。
他のジョーンズの作品と同様に、相変わらず猫が重要な役回りを果たしていますが今回の猫は、 キャットが練習しているときに、グェンドリンが「うるさい」と魔法で猫にしてしまった「フィドル」という子です。
しかし、これもいつもの事ながら、登場するのはなかなか共感できない人物達です。 大抵児童書は人物形成も単純化して読者に感情移入しやすくしてあるものですが、この本に関してはそういった年少読者に対する「媚び」とは無関係のようです。 気位が高くて選民思想のある鼻持ちならないグェンドリンが、何時かは高慢な鼻を折られて、かわいそうなキャットを大事にするようになるだろう、などと甘いことを思っていたら大間違いでした。
彼女はあくまでも自己中心的で、自分の野望のためには弟まで生贄にせんとする本物の「魔女」ぶりを人前に曝します。
ジョーンズにとっては甘い姉弟関係の修復よりも大団円へ広がった話を収束させていくプロットの方を優先させたみたいです。逆説的ですが、世によくある姉弟間の軋轢の解消などという 家庭ドラマに終始しなかったからこそ、読んでいて全ての疑問が適度なユーモアを交えて解き明かされて行くのを逐一辿る快感が得られるのだと思います。
道具立てだけ魔法や魔女やドラゴンを配して「ファンタジー」を標榜するだけのなんちゃってファンタジー作品と違って、このシリーズには魔法や別の重層世界が、ごく日常の事柄として存在する世界で 一人の少年が自己を発見する、狭義のファンタジー枠を越えた骨太の構成があるので、多少のことでは感心しないすれっからし読者の私なども、大変楽しむことができたのだと思います。
九年目の魔法 ダイアナ・ウィン・ジョーンズ

 ハリー・ポッターと指輪物語ブームにあやかって、ここしばらく日の目を見なかったファンタジー関連本を売らんかな…そういう下心が見え透いた魔法、
ファンタジー本が書店の目立つところに平積みされている。
ハリー・ポッターと指輪物語ブームにあやかって、ここしばらく日の目を見なかったファンタジー関連本を売らんかな…そういう下心が見え透いた魔法、
ファンタジー本が書店の目立つところに平積みされている。何事に寄らず一過性のブームにわっと湧く世間大衆に、苦々しい思いを禁じ得ないのが、 氷河期に細々と読み継ぎ語り継ぎ、周囲の好奇の目に耐えてきた自称真性ファン。
でもそんな人だって最初に開眼したときは新参者だったし、先人は必ず居たのだから、 目くじら立てずに、氷河期の終わりを寿ぎ同好の士が一人でも多く増えるのを喜ばなくちゃ。
これは一体何のまくらかというと、私もその平積み本の一冊に手を伸ばし その不思議な手に絡め取られてしまったからです。
"Fire and Hemlock"(邦題「九年目の魔法」)ダイアナ・ウィン・ジョーンズ、この作品を読んで、 (そもそも比較するのが無理なのですが)ハリー・ポッターは分かりやすい児童書なのだと再認識しました。
この作品というと、読みながら一抹の不安を頭からぬぐい去れないのです。 主人公のポーリィ、19才はある日唐突に見慣れた絵と読み慣れた自分の記憶が微妙なところで食い違いを見せている事に気がつきます。
焦燥のうちに10才からの記憶を辿って行きますが、 10才の折りに出会ったチェリストのリンさんを思い出します。彼と想像のお話しごっこをするのですが、どこまでが現実でどこからが幻想か、更にどこまでが本当の記憶で、どこまでがすり替えられた偽の記憶なのか ……今の今まで疑いもなく確固としてあった過去が一挙にあやふやな記憶の錯綜へ姿を変えていきます。
ポーリィーと共に読者もオブラートのかかった記憶の海に孤舟で 沖に押しやられてしまいます。
誰が一体何のためにポーリィとリンさんを想像と現実の間で翻弄するのか、リンさんが遠出する先々からポーリィーに送ってくるファンタジーの本は何を示唆しているのか 、各章の冒頭に引用されている詩の一節は何を暗喩しているのか?
"少女と魔法、愛と成長のファンタジー"なんていう砂糖菓子みたいな本の腰巻きに書かれているキャッチコピーに惑わされてはいけませんよ。
そんな歯触りのいい言葉で「たわいもないお話」に分類してしまうのはもったいない物語です。読み終わってもう一度、読み落とした部分を探すために最初からページを繰ってみたくなる話です。
今までこの作家、この作品を知らなかった……新しく目を開いてくれた本に出会うたびに、この邂逅へと導いてくれた偶然、(それともそれを運命論者は運命と呼ぶのだろうけれど)それに感謝したくなります。
さて今日から「わたしが幽霊だったとき」(The Time of the Ghost)に取りかかるとしましょう。
余談ですがこの2作品を翻訳したのは"クリスタルシンガー""キラシャンドラ"と同じ浅羽莢子さんです。
2001/12/10 記
クリスタル・シンガー アン・マキャフリー
 Crystal Singer--クリスタル・シンガー この一文は以前にネタバレ掲示板「見るなの部屋」に投稿したものです。一応書籍の紹介なのでこちらへ転載します。
Crystal Singer--クリスタル・シンガー この一文は以前にネタバレ掲示板「見るなの部屋」に投稿したものです。一応書籍の紹介なのでこちらへ転載します。イギリスの作家、アン・マキャフリーの手による「クリスタルシンガー」、「キラシャンドラ」、「クリスタルライン」、これがキラシャンドラ3部作です。 1,2作は翻訳が出ていますが第3作目は未訳です。
純然たるSFですが、マキャフリーの他のシリーズ:歌う船のシェルパーソン、パーンのドラゴンライダー、 ライアン家の九惑星、ペガサスのESP、惑星アイリータ、フリーダム等とまたひと味違う、とても私小説的作品です。
先ずその舞台設定がちょと変わっています。 ボーリーブランという危険度4(立入禁止)の惑星があってそこの特産はクリスタル。クリスタルは同調した固有の分子振動を持ち、宇宙船の推進機関に用いられると共に、 星間通信に用いるとタイムラグ無しでどんな遠距離通信もできる代物。
種類は白・青・バラなど色々あるのですが最高の品質を持つのが黒クリスタル。 しかし黒クリスタルはきわめて稀少で一山あてると大変な財産になるのです。
さて、このクリスタルを鉱脈を見つけ、そこから結晶を壊さずに、 しかもなるだけ大きく切り出す特殊技能を持つ職業集団(ギルド)があります。これがクリスタル採鉱士、別名クリスタルシンガー。なぜクリスタル歌いと呼ばれるのかというと、 クリスタルを切り出すには特殊な音波カッターをクリスタルの固有振動数にぴったり合わせないといけない、つまり絶対音感がなければいけないのです。 シンガーは自分で音程を取ってクリスタルを歌いながらカッターで切り出します。
広大なボーリーブランの山また山の世界に少数のシンガーが「ソリ」を飛ばして鉱脈を探すために 何日も孤独な旅を続けます。そして、一旦鉱脈を探し当てたら寝食も忘れてカッターで切り出します。というのも、ボーリーブランの気象は変化が激しく、嵐が接近したらすぐに 基地に帰らないと外でマッハ嵐に遭う事は死を意味するからです。しかも嵐は想像を絶する強さで、山の形は変わり、クリスタルは砕けてしまうので後日改めて切り出しに行くといった 悠長な事は言っていられないのです。だから後述するクリスタルとの交歓の魅惑に打ち勝ちながら如何に手際よく切り出すか、これがまたシンガーの腕になるわけです。
さて、シンガーになるには実は絶対音感が必要なだけではなく、もう一つ大きなハードルがあります。ボーリーブランは一度足を踏み入れたら二度と出られない世界───それが危険度4 の示す所なのですが───この惑星の大気中には特殊な微生物がいてこれが人間と共生状態にはいるのです。共生に移行するまでが危険で命を失うものもいます。共生状態になっても何らかの感覚失調という代償がつきまといます。ここで聴覚を失ったらもうシンガーにはなれません。しかもこの共生生物は母星ボーリーブランを離れては 生きられ無い上に共生生物が死ねばホストも運命を共にします。シンガーを夢見てここに来た候補者の多くは結局シンガーにはなれず、しかもここから出ていけない、 そういう運命を辿ります。
さらに状況を複雑にしていることに、ボーリーブランにはマッハ嵐という超度級の気象変動が起こるのです。二つの衛星との潮汐作用による、 この「過ぎ越し」を星外で過ごさないと嵐の立てる壮絶な音で気が狂ってしまうという恐ろしい事実があります。だからシンガーたちは過ぎ越しの既刊に先を争って星外へ出るのに 十分なクレジットを稼ごうと躍起になるのです
もちろん、これらのマイナスを補って余るプラスもあります。この共生生物のお陰でホストは不死身に近い状態になります。 ほとんどの怪我は一日で治ってしまうし、寿命は有に300歳以上になります(しかも老けないで)ただしこれが大きなポイントなのですが、記憶がどんどん減退していって最後には 自分が誰かも忘れてしまうのです!!何という設定でしょう!
さてここに登場しましたキラシャンドラ、オペラ歌手になろうと10年も修行したのに声に問題ありという理由で コーラスに下げられることが決定して、それを潔しとしないで音大を飛び出します。偶然にボーリーブランから「過ぎ越し」で避難していたシンガーと知り合いになって自分も シンガーになろうと思い立ちます。
これからほんの少しの「挫折」と抱えきれないほどの「成功」の物語が始まります。まったくのサクセスストーリーでキラは トントン拍子で共生を理想的に乗り切り、ギルド会長の個人的な好意を得て、しかも最初の仕事で黒クリタルの鉱山を吾がものにして・・・・・・
名誉と金といい男まで手に入れて、 こんないい話ちょっと他にはありませんね。落ち込んでいるとき、疲れたときには読み直すといい話です。単なるシンデレラ・サクセスストーリーと少し違うところは、 キラが自分の運命を強く自分で切り開くところ、それにクリスタルとの交歓がいかに魅力的で忘我の境地を誘うものかが細かく描写されているあたり、こんな恍惚感を味わってみたいと 思わない人はいないのではないでしょうか。
クリスタルを歌うと無人の山全体がドミナントの協和音を奏でて振動します。響きに包まれて片手に切り出したばかりの黒クリスタル結晶を 持って恍惚の忘我の境地をさまよいます。そして、はっと気付くと半日くらい経っているのです。この部分の描写を読むだけでも価値があると思いますが、 いかがなものでしょうか。
余談ですが中で語られる多様な食物やビールなど飲料に関する記述もなかなか楽しくこちらの食欲もそそられます。
アヴァロンの闇 ラリィ・ニーヴン,ジェリー・ポーネル&スティーブン・バーンズ
アヴァロン、キャメロット、グレンデル、ベーオウルフ……このキーワードだけ聞いてこれが純SFだと気がついた人がいたら脱帽である。そうはいっても、ラリィ・ニーブンの名でそれと気付かなかったこちらにも落ち度はあるのだが。
鯨座タウ星第4惑星、アヴァロン、地球から20光年の距離を冷凍睡眠をしてたどり着いた160名余りの植民者が降り立ったのはキャメロットと名付けられることになる島だった。人間よりも大きな生物は全く生息しない、その名の通り美しい平和そのものの世界────地球から植民船に搭載してきた物資でコロニーを作り、生物の胚を解凍して牛や馬、 家禽を育成し、澄んだ川にナマズを養殖した。唯一大きな鳥くらいのプテラノドン(そう人々は呼んでいる)は極めて臆病で水中に生息する"サケもどき"を捕る時でもびくついている くらいである。人々はアヴァロンをついの住処とするべく子供を儲け出す。唯一、計算外だったのは〈人工冬眠の不安定性〉といわれる冷凍冬眠の後遺症だった。 地球の選りすぐりの優秀な頭脳の持ち主を選択したのに冷凍冬眠から冷めたときに脳に何らかの損傷を受けてしまう、その結果、明晰な頭脳を失ったり、過去の知識を失ったり、 影響のない者ももちろんいるのだが。
主人公のキャドマンはコロニーの保安要員として参加した。ところが平和そのもののキャメロットでは出番はない、最初こそ外敵に対する警戒もあったが時間の経過と共に戦士は無用の長物と化す。
ここに登場するするのが"それ"……アヴァロンの川に住む両棲類、肉食でその獰猛性のために個体数は少なく厳密に住み分けをしている。"それ"が自分のなわばりに住み着いたよそ者に気付き外縁に忍び寄る。先ず、ナマズ、次ぎに犬、 子牛と被害が広がるが人々は怪物の存在には半信半疑である。いち早く未知の生物の脅威を説くキャドマンは冷笑を浴びせられる。
そして……"それ"の襲撃が起こる。
ここから後はまさにジェットコースターのように話が独りでに展開していく。たった1匹のそれ────人々はベオウルフにちなんで"グレンデル"とよぶのだが──── のために20人が死に多数が負傷する、グレンデルの傍若無人さはまさに"エイリアン"を彷彿とさせる。生身の素手の人間など濡れ紙のように叩きつけられて行く。
「異星怪物と戦う人間」、古典的テーマで息つく暇もなく一気に読ませるテクニックは大した物である。その凄まじい力業に読者サイドも巻き込まれ登場人物達の奮闘の渦に飲まれて 最後までページを繰り続けるのだ。ある意味、最後は肉弾戦で巨大な怪物に立ち向かう原初的な生存のための闘いの持つ粗削りの生の感触、疾うの昔に失われた、映画"エイリアン2"や"プレデター"にも共通するバトル小説。
面白いのはグレンデルのサイドからの書き込みがあること。この辺りかのA.E.ヴァン・ヴォートの" 宇宙船ビーグル号の冒険"の第1話に登場する"クァール"(本によってはケアル)を彷彿とさせる。グレンデルの原初的な衝動、欲求、憤怒などが体感できる。
グレンデルの肉体の"スーパーチャージャー"構造も面白いし、生態上の落とし穴────それに関する無知が上巻では一旦グレンデルを絶滅させたかと思った人間の勝利を下巻では粉々に打ち砕くのである────圧倒的な物量の描写は手に汗握るものがある。映像化したらきっと面白いだろうと想像を逞しくしてしまった。
サイドストーリーとして限られた人員の中での三角関係や主人公の奮戦ぶりなどあるが、こちらはいくらページを裂いていても余り印象に残らない。徹頭徹尾、 人間対怪物の血みどろのサバイバルゲームの小説と言えよう。────だからこそ 面白いのである。だからこそ一気に上下巻読み通させるエネルギーを持っているのである。
沈まぬ太陽 山崎豊子
 読書家の友人の薦めで手に取りましたが、読みやすく5巻一気読みに近い状態で読めました。
読書家の友人の薦めで手に取りましたが、読みやすく5巻一気読みに近い状態で読めました。大まかに内容的に3部に分けられる。第1部は巨大航空機産業の一社員が組合運動に関わり、その節を曲げなかったために海外僻地勤務を10年余に渡り強いられる。
第2部、かろうじて日本勤務に戻れば、今度は時悪く御巣鷹山航空機事故担当に回されて現世の地獄を見る。
第3部、放漫経営を立て直すべく政府肝いりで就任した新会長の信認を受け抜擢されるも政界と癒着した経営陣の妨害に会い、改革半ばで会長辞任、主人公も再び海外勤務に左遷される。
誠実に節を通した人間が企業という巨悪の中で理不尽にも虐げられていく受難の書。本音を言うと4,5巻目には同工が目立ちいささか辟易したが、主人公の潔さと未来への信頼が救いになっている。3巻の御巣鷹山編は当事者へのインタビューを駆使して書かれており、事実の重みに圧倒される。 このレビューを書いた後に、本作品の主人公のモデルとなった実在の元社員の方が70代前半でなくなられたと小さく新聞記事にあった。
物語の旅 和田 誠
 本について語るのにちょうどいい長さがあるように思います。
本について語るのにちょうどいい長さがあるように思います。語りすぎず、おざなりでもなく、あらすじの紹介に留まらず、小難しい評論にも終始せず。
この本はその条件を全て満たしています。 54の物語の紹介、著者の言葉を借りれば『物語に対するささやかな四方山ばなしである。自分にとって印象の深かった書物についてごく個人的な事を記すだけだ……』 この言葉の通り色々な書物がアトランダムに、全て3頁ずつ。全編に著者の手によるイラストがついています。
目次を見るなりこの本を購入したわけは、選ばれている54編の多くにかなりマイナーな作品を含み、しかもそのマイナー作品が、 その道のちょっと訳知りには堪えられないいい味を持った作品が多いからでした。
まあ、いってしまえば何のことはない、 私の趣味とよくあっていたということに尽きるようです。頭から紹介してみましょう……
・かちかち山 ・西遊記 ・アリババと40人の盗賊 ・古事記 ・魔法の杖 ・ ライオンのめがね ・豹(ジャガー)の眼 ・火星兵団 ・ほら吹き男爵の冒険 ・くまのプーさん ・ビルマの竪琴 ・宝島 ・トム・ソーヤーの冒険 ・信州天馬侠 ・月夜のでんしんばしら ・杜子春 ・山椒大夫 ・813 ・黄金虫 ・緋色の研究 ・夢十夜 ・そして誰もいなくなった ・ドルリー・レーン最後の事件・失われた混合酒 ・旧約聖書 ・鏡地獄 ・血の収穫 ・ねじの回転 ・ 快盗ルビイ・マーチンスン ・あるスパイへの墓碑銘 ・半七捕物帖 ・点と線 ・長いお別れ ・マクベス殺人事件 ・南からきた男 ・キリマンジャロの雪 ・人形使い ・雨月物語 ・けんかえれじい ・柳 ・甲賀忍法帳・ジャングル放浪記 ・骨餓身峠死人葛 ・群猫 ・アシェンデン ・霧笛 ・江戸の夕立 ・麻雀放浪記 ・横しぐれ ・シャドー81 ・踊る小人 ・深夜プラス1 ・毒猿 ・最後の仇討
どうでしょう、読みたくなりませんか?
個人的には、筒井康隆「群猫」やルブラン「813」、 ロス「ドルリー・レーン最後の事件」、ハインライン「人形つかい」、野坂昭如「骨餓身峠死人葛」など、遙か昔に読んで今はもう思い出すことも余りなかった 物語と改めて対面して、それらを呼んだときのみずみずしい感動を思い出すことができました。
個々の四方山話を読み進むうちに著者の幼年時代から少年時代、青春を経て大人になり今日に至る軌跡が、そこここで私のそれと重なり合って、以前に読んで、その面白かったこと、心を打たれた事は鮮明に覚えていても、 内容は少しずつ忘却の中に薄れつつあった、いくらかの書物を再確認し、また知る機会のなかった書物への興味をかき立てられました。
本を読むというのはまさに個人的な行為であり、その書物に対する思いもまさに個別的なものであるはずなのに、その排他性ゆえに、図らずもその思いが共有できる時に人は、 その相手に限りない親近感を抱き、第二の自己、自己の分身の様に身近に感じることができるのでしょう。
ランドオーヴァー=シリーズ テリー・ブルックス
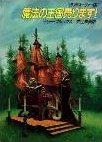 ランドオーヴァーーシリーズは5作の連作になっています。順に「魔法の国売ります」「黒いユニコーン」「魔術師の大失敗」「大魔王の逆襲」「見習い魔女にご用心」。
ランドオーヴァーーシリーズは5作の連作になっています。順に「魔法の国売ります」「黒いユニコーン」「魔術師の大失敗」「大魔王の逆襲」「見習い魔女にご用心」。ファンタジー専門に鞍替えしたわけではないのですが、購入だけしておいて読んでなかった5冊を年末年始にかけて読みました。
そもそも、自分の好みを言えば、 アプリオリに騎士や魔法使い、はてはドラゴンやエルフが当然のように出てくる、耳慣れない地理と歴史に翻弄されるそういったタイプのハイ・ファンタジー(もしくはファンタジーもどき)は いくら読んでみようとしても、どうも拒否反応をおこしてしまいます。
一方、モダンファンタジーと呼ばれる(これがジャンルとして根付いているのかはさておいて) 作品群では、ファンタジー世界があくまで現実のこちらの世界との接点を失ってはおらず、むしろこちらの現実社会の中にファンタジー世界が浸透して来ている設定で物語が進展します。
ハイ・ファンタジーを読む上で、全くの架空の世界と、架空の世界を支えるコンセプトを納得かつ理解して、しかも親しみを感じるまでになるには、作者の筆力は言うまでもなく、 読者の根気と大いなる空想力と、些細な事には目をつむる鷹揚さが必要です。
一旦、その非現実性を考慮してもそれを上まる堅固な物語性に人気を博した作品は 作者の構築した世界の物語をあまねく隅々まで語るために、シリーズ化して語り足りぬ処を、別伝、外伝と補筆して、際限なく拡散していくようです。
ランドオーヴァーもその手の話かと長らく思っていました。ランドオーヴァーを購入した直接のきっかけは、作者テリー・ブルックスが書いた「妖魔のすむ街」がかなり気に入ったからです。 ついでに言うとテリー・ブルックスは映画「フック」や「SWエピソード1」のノヴェライゼーションの著者でもあります。癖のない文体と細やかな表現を得意とするところがこの大任に抜擢された所以でしょう。
話が戻りますがランドオーヴァーの物語では、現実のアメリカとファンタジー世界の王国が隣接していて、まるで潜り穴を抜けるようにして行き来ができることになっています。
その世界たるやマーリンもどきの大魔法使いから、魔法で犬になってしまった宮廷書記、コボルト、窪地の魔女、最後のドラゴン、王を守る伝説の騎士、緑の髪の水と木のエルフ、ゴーホーム・ノームの訛ったゴホーム・ノーム・・・・・・ そりゃもう盛りだくさん
その魔法の王国の王になったのは壮年のアメリカの弁護士ホリディ。
どうやって王国の主になったか? はい、クリスマスの広告に売りに出ていたのを買ったんですね。
つまり(後書きにもあるように)テーマパークよろしく一式揃った魔法の王国を一人の弁護士が100万ドルで 購入したわけです。第1巻は王の権威が地に落ちているランドオーヴァーを半人前魔術師のクエスター・スーズと犬人間のアバーナシィーと二人組のコボルトの協力を得ながら、 なんとか諸侯を王の権威に従わせシルフの恋人もでき、ドラゴン、魔女とも何とか休戦協定を結び、王の騎士パラディンを召還して一体になることで最大の危機を乗り切って、 晴れてランドオーヴァー王になるまでを綴っています。
通販カタログで王国を手に入れるところ、おまけに気に入らなければ10日のクーリング・オフまで付いている代物。 主人公は実社会では成功しているものの、最愛の妻と子供を事故でなくしてから空虚な日々を送っています。何かの冗談だろうと広告に応じたところあ、あれよあれよという間に魔法の王国の 売買契約は発効してしまって、ホリディは、自分がほとんど何の実権も持たない王である状態へ放り出されていることに気がつきます。 さて、気を取り直した実務化のホリディが先ず着手したのは、ランドオーヴァーを法治国家として再建することでした。
現代人の理性と心証を持ちながら、舞台はファンタジー魔法王国。巻を追うごとに現代アメリカとランドオーヴァーの接点が開いて予期せぬ人がこちらに送られて来て、 あちらに帰るべく苦心惨憺したり、(この時にはこちらにドラゴンまで出現させてしまいます)、こちらに亡命していた、魔法使いが魔の唐草箱を開けて、 封印させていた大魔王が復活したり、そのたびにホリディはアイデンティティーの危機に立たされながら事態を収拾。ついには娘が生まれ、強大な魔女の素質を持っているが故に 悪い窪地の魔女に利用され、父王を苦しめる結果になります。
進化型ファンタジー。新しい展開、新しい登場人物、自足的なオーソドックスファンタジーに対して軽妙洒脱、エンタティンメントに徹した、そう、 まるでTVシリーズ物ドラマにしたらいいような筋立て、道具立てです。
こういった純粋に楽しめる物がまだファンタジーには少ないように思われます。 今後もシリーズ続巻が一日も早く出ないかと待たれる所以です。
ファンタジーの冒険 小谷真理
 一年前なら手にも取らなかっただろう本である。そもそも"ファンタジー"と堂々と銘打ってある新書など、こちらが気恥ずかしくなってしまったであろう。
一年前なら手にも取らなかっただろう本である。そもそも"ファンタジー"と堂々と銘打ってある新書など、こちらが気恥ずかしくなってしまったであろう。そう考えてみると、昨今のハリー・ポッターシリーズが世界的に好評を持って受け入れられたのに始まり、その映画化、トールキンの"指輪物語"の映画化が矢継ぎ早に行われて、まさに新千年紀に入ってファンタジーの復権、ファンタジーの復興が現実のものとなった────そのような大きな世間の風潮の変化が、 それ以前にファンタジーの洗礼を受けながら、ファンタジーの持つ特異なプロット、表現法、外装故にファンタジーファンを標榜するのに抵抗を感じていた人々に、改めてファンタジーへの回帰を促すことに一役かったと言えるであろう。
今なぜファンタジーか? この問いかけをよく眼にするが、問いそのものが皮相である。ファンタジーは昨日今日に生まれてきたものではない、おそらく人類が農耕定住を始め、一定の人口を養うだけの安定した生産性を確保した頃から発生してきた最も原初的な文学はファンタジーの形をしていたのであろう。
ファンタジーは現実主義と対極にあるように理解されているが、現実の否定の上に成り立つものではない。鋭敏な現実に対する感覚こそがファンタジーを生み出す土壌であった。現実の枠にはまりきらない奔放な空想力を受け止めたのがファンタジーというジャンルだった。 本書はモダン・ファンタジーに焦点を絞って19世紀の英国の妖精物語から始まり、戦前のパルプ・フィクション、ラヴクラフト=クトゥルフ神話、戦後60年代のニュー・ウェーブ・ファンタジーに現れたC.S.ルイス、トールキンの指輪、アーサリアン・ポップの諸作品、70年代フェミニズム運動と呼応した女性ファンタジーの駘蕩、現代に至るハイテク革命とファンタジーの変容について、それぞれ1章ずつ当てて豊富な作品の内容紹介とファンタジージャンル全体における位置づけをわかりやすく解説している。
余談になるが、後書きに筆者が記されていた所によると、筆者が最初に読んだファンタジーがエリザベス・グージの「まぼろしの白馬」であったそうだ。その出会いといい、物語に夢中になった経緯といい、私の場合と余りにも似ているのに、思わず眼を疑った。筆者と年齢も近いし出身も一県離れた隣接県であったことも、何か共通の感じ方をした理由の一つかも知れない。
私たちも時代精神というものの轍から逃れられていないのかと考えることもできるが、単純に同じような年映えの小学生が同じ頃に同じ物語に夢を馳せたのかと懐古的に思えばこれもまた善哉である
↑ ページトップに戻る